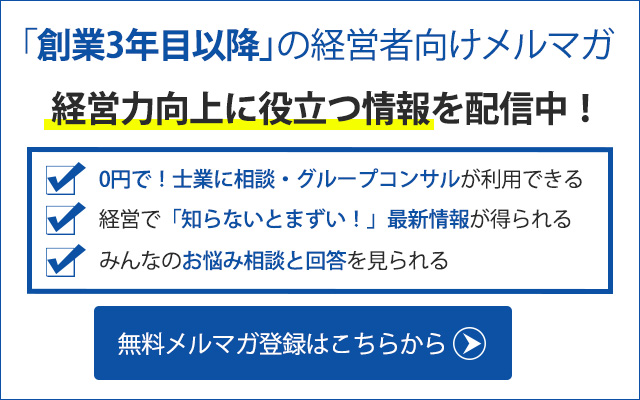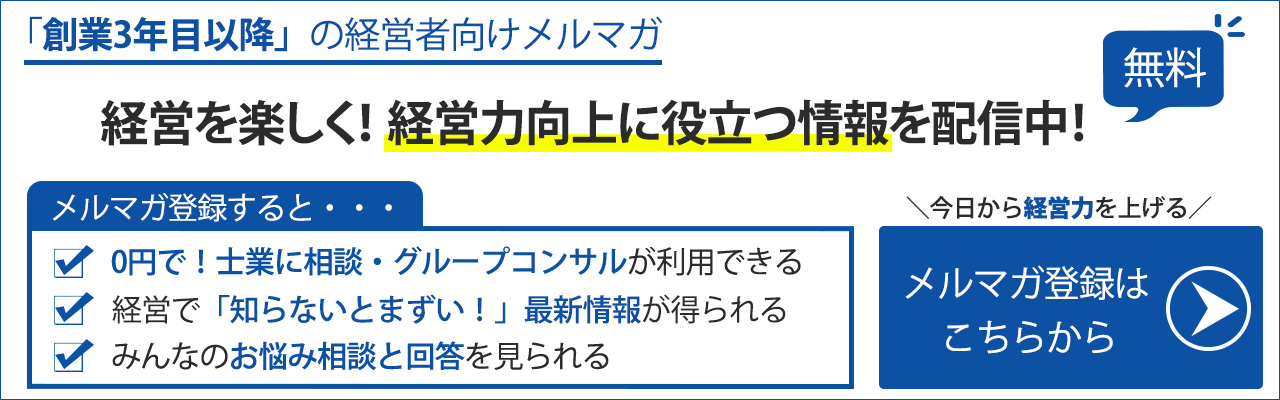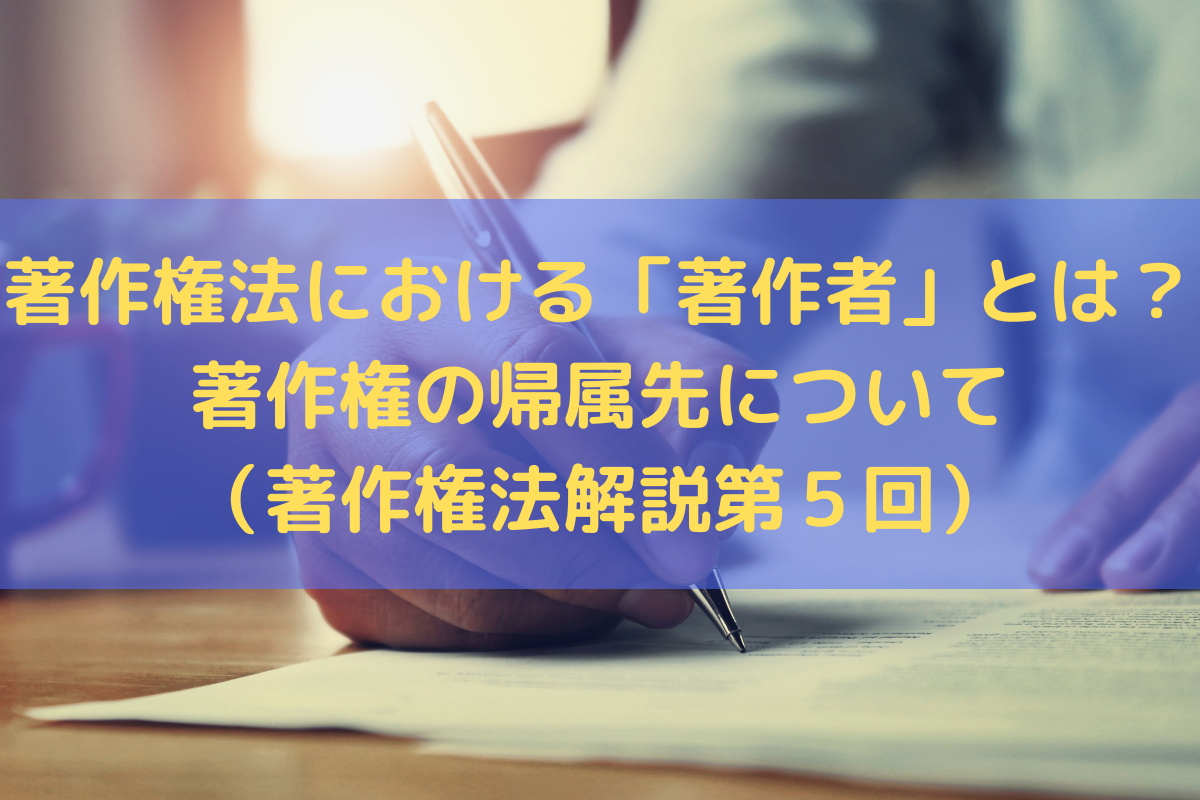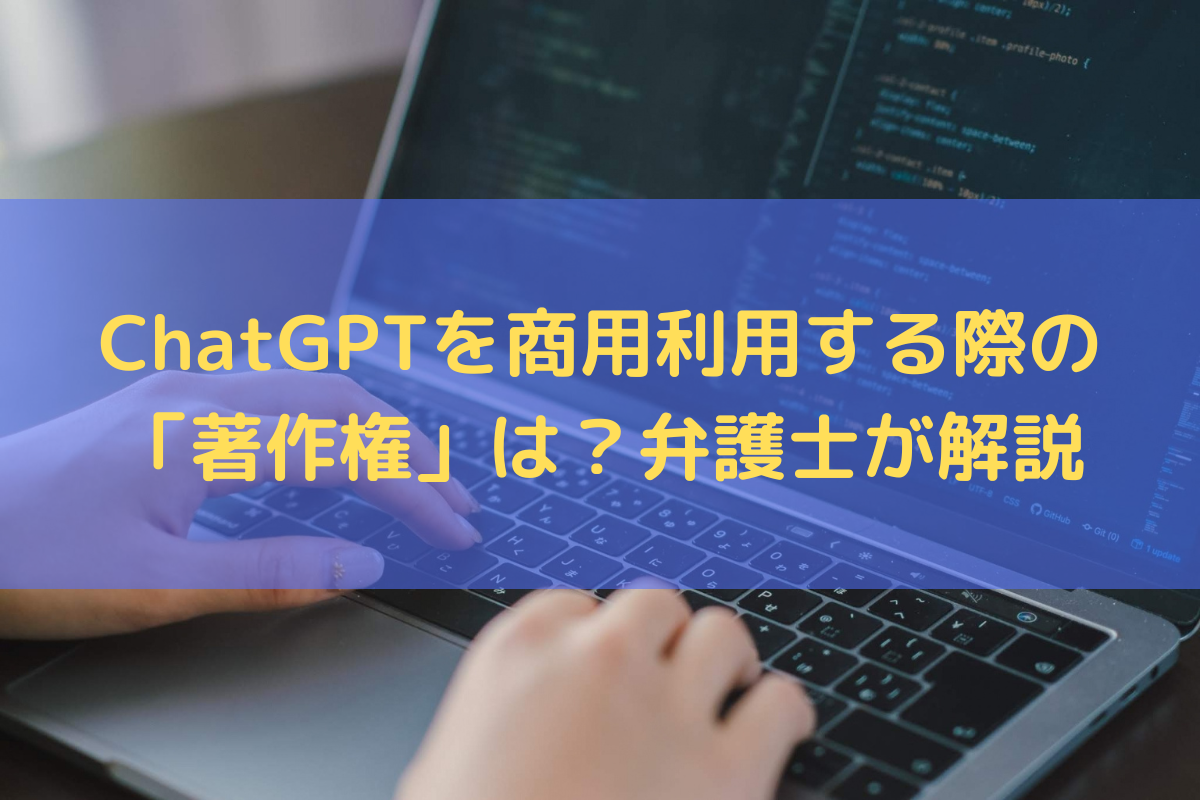音楽教室事件(JASRACvs音楽教室)知財高裁判決解説
目次
1. はじめに
音楽教室での演奏をめぐり、ヤマハ音楽振興会等の音楽教室事業者が、JASRAC(日本音楽著作権協会)に、著作権使用料の徴収権がないことの確認を求めた訴訟(以下、「音楽教室事件」)の控訴審判決が2021年3月18日、知財高裁でありました。
知財高裁は、JASRACに徴収権限があるとした一審の東京地裁判決を一部変更し、生徒の演奏については著作権使用料を徴収できないと判断しました。
【関連コラム】
【判決文へのリンク】
2. 事案の概要
本件は、音楽教室を運営する音楽教室事業者(以下、「原告ら」)が、著作権管理事業者であるJASRAC(以下、「被告」)を相手取り、音楽教室でのレッスンで被告管理楽曲を演奏することについて、被告が原告らに対して著作権(演奏権)侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有していないことの確認を求めた事案です。
3. 裁判の争点
前述のとおり、本件の主な争点は、音楽教室での被告管理楽曲の演奏につき、演奏権侵害が認められるかどうかです。
ここで「演奏権」とは、著作者が専有する権利の一つで、公衆に直接聞かせることを目的として演奏(歌唱を含む)する権利をいいます(著作権法22条)。また、「公衆」とは、「特定かつ少数以外の者(不特定又は多数の者)」を指します(著作権法2条5項)。
つまり、本件で演奏権侵害が成立するには、音楽教室における演奏が1.公衆(不特定又は多数の者相手)に直接聞かせることを目的として行われたものであることが要件となります。
さらに、上記の「公衆に直接聞かせることを目的」として行われたものであるかの判断にあたっては、2. 音楽著作物である被告管理楽曲の利用主体も重要なポイントとなります。
まず、2つ目の「音楽著作物の利用主体」についてですが、一般的な感覚からすれば、「現実に著作物の利用行為を行っている者は誰か」、すなわち、「実際に演奏をしている者は誰か」によって導かれるものだと考えられます。しかし、著作権法では、現実に著作物を利用しているとは言い難い者であっても、著作物の利用行為の主体とする考え方があるため、実際に演奏を行っている者(教師や生徒)がその利用主体になるとは限りません。
この考え方は、「カラオケ法理」と呼ばれるもので、次の要件を満たす者については、著作権法上の規律の観点から利用行為の主体であると評価されます(最判S63.3.15「クラブキャッツアイ事件」)。
- 著作物の利用行為を管理すること
- 著作物の利用行為により利益を得ることを意図していること
4. 知財高裁の判断
では、これらのことを踏まえて、知財高裁判決の内容を見ていきましょう。
5.1 はじめに
A. 音楽著作物の利用主体について
まず、知財高裁は音楽教室における音楽著作物の利用主体の判断基準つき、「ロクラクⅡ事件(最判H23.1.20)」を引用して次のように判示しました。
※以下、本コラムでは説明のしやすさの観点から判決文中の「控訴人ら」は「原告ら」に本コラム中では置き換えています。また引用内の下線部は筆者によるものです。
原告らの音楽教室のレッスンにおける教師及び生徒の演奏は、営利を目的とする音楽教室事業の遂行の過程において、その一環として行われるものであるところ、音楽教室事業の上記内容や性質等に照らすと、音楽教室で利用される音楽著作物の利用主体については、単に個々の教室における演奏の主体を物理的・自然的に観察するのみではなく、音楽教育事業の実態を踏まえ、その社会的、経済的側面も含めて総合的かつ規範的に判断されるべきである。
音楽教室における演奏の主体の判断に当たっては、演奏の対象、方法、演奏への関与の内容、程度等の諸要素を考慮し、誰が当該音楽著作物の演奏をしているかを判断するのが相当である。
B. 「①公衆に直接②聞かせることを目的として」について
つぎに、知財高裁は、演奏権侵害の要件である「①公衆に直接②聞かせることを目的」の判断につき、以下のように述べました。
- 公衆にあたらない「特定かつ少数」の「特定」とは、演奏権の主体となる演奏を聞かせようとする目的の相手方との間に個人的な結合関係があることをいう
- 「直接」聞かせることは、演奏者が面前にいる相手方に聞かせることを目的として演奏することを求める
- 自分自身が演奏主体である場合は「公衆」に該当しない
- 「聞かせることを目的」とは、演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らし、演奏者に「公衆」に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる場合をいう
そのうえで、音楽教室における演奏が上記の要件を満たすのは以下の場合であると判示しました。
演奏者が、①面前にいる個人的な人的結合関係のない者に対して、又は、面前にいる個人的な結合関係のある多数の者に対して、②演奏が行われる外形的・客観的な状況に照らして演奏者に上記①の者に演奏を聞かせる目的意思があったと認められる状況で演奏をした場合と解される。
5.2 教師による演奏について
A. 音楽著作物の利用主体について
これらの考えをもとに、知財高裁は、音楽教室における演奏を、教師による演奏と生徒による演奏とで区別して検討・判断しました。
まず、教師がした演奏の主体については、前記5.1A.で示した判断基準に基づき、以下のようにその主体を“音楽教室事業者たる原告ら”であると認定しました。
ケース1:教師を兼ねる音楽教室事業者(個人事業主)や、個人教室を運営する各原告らが教師として自ら演奏を行う場合
⇒その主体は音楽教室事業者である原告らであることは明らかである。
ケース2:音楽教室事業者ではない教師が演奏を行う場合
⇒原告らが教師に対して、本件受講契約の本旨に従った演奏行為を、雇用契約又は準委任契約に基づく法的義務の履行として求め、必要な指示や監督をしながらその管理支配下において演奏させていることから、教師がした演奏の主体は規範的観点に立てば、原告らであるというべきである。
B. 「①公衆に直接②聞かせることを目的として」について
①「公衆」に直接について
そして、「原告ら」を利用主体と認定したうえで、生徒の「公衆」への該当性について、前記5.1B.①の解釈に基づき以下のように述べ、音楽教室の生徒は、「公衆」にあたると判断しました。
原告らと生徒の当該契約から個人的結合関係が生じることはなく、生徒は原告ら音楽教室事業者との関係において、不特定の者との性質を保有し続けると理解するのが相当である。したがって、音楽教室事業者である原告らからみて、その生徒は、その人数に関わりなく、いずれも「不特定」の者に当たり、「公衆」になるというべきである。
②「聞かせることを目的」について
また、「聞かせることを目的」への該当性についても、前記5.1B.②の解釈に基づき以下のように述べ、教師による演奏は、公衆である生徒に対して「聞かせることを目的」で行われるものにあたるとしました。
原告らの音楽教室におけるレッスンは、教師又は再生音源による演奏を行って生徒に課題曲を聞かせることと、これを聞いた生徒が課題曲の演奏を行って教師に聞いてもらうことを繰り返す中で、演奏技術等の教授を行うものであるから、教師又は再生音源による演奏が公衆である生徒に対し聞かせる目的で行われていることは、明らかである。
C. 小括
以上のことから、教師による演奏については、その行為の本質に照らし、本件受講契約に基づき教授義務を負う“音楽教室事業者”が行為主体となり、不特定の者として「公衆」に該当する生徒に対し、「聞かせることを目的」として行われるものというべきであるとしました。
5.3 生徒による演奏行為について
A. 生徒による演奏行為の本質について
一方で、生徒がした演奏の主体の判断にあたって、その演奏行為の本質について、本件受講契約に基づく音楽及び演奏技術等の教授を受けるため、教師に聞かせようとして行われるものとしたうえで、以下のように述べました。
音楽教室においては、生徒の演奏は、教師の指導を仰ぐために専ら教師に向けてされているのであり、他の生徒に向けてされているとはいえないから、当該演奏をする生徒は他の生徒に「聞かせる目的」で演奏しているのではないというべきであるし、自らに「聞かせる目的」のものともいえないことは明らかである(自らに聞かせるためであれば、ことさら音楽教室で演奏する必要はない。)
B. 演奏主体について
つぎに、生徒のした演奏の主体について検討しところ、以下のような見解を示しました。
生徒は、原告らとの間で締結した本件受講契約に基づく給付としての楽器の演奏技術等の教授を受けるためレッスンに参加しているのであるから、教授を受ける権利を有し、これに対して受講料を支払う義務はあるが、所定水準以上の演奏を行う義務や演奏技術等を向上させる義務を教師又は原告らのいずれに対しても負ってはおらず、その演奏は、専ら、自らの演奏技術等の向上を目的として自らのために行うものであるし、また、生徒の任意かつ自主的な姿勢に任されているものであって、音楽教室事業者である原告らが、任意の促しを超えて、その演奏を法律上も事実上も強制することはできない。
~(中略)~
音楽教室における生徒の演奏の本質は、あくまで教師に演奏を聞かせ、指導を受けること自体にあるというべきであり、原告らによる楽曲の選定、楽器、設備等の提供、設置は、個別の取決めに基づく副次的な準備行為、環境整備にすぎず、教師が原告らの管理支配下にあることの考慮事情の一つにはなるとしても,原告らの顧客たる生徒が原告らの管理支配下にあることを示すものではなく、いわんや生徒の演奏それ自体に対する直接的な関与を示す事情とはいえない。
これらのことから、以下のように述べ、生徒がした演奏については、その主体を“生徒”であると認定しました。
生徒は、専ら自らの演奏技術等の向上のために任意かつ自主的に演奏を行なっており、原告らは、その演奏の対象、方法について一定の準備行為や環境整備をしているとはいえても、教授を受けるための演奏行為の本質からみて、生徒がした演奏を原告らがした演奏とみることは困難といわざるを得ず、生徒がした演奏の主体は、生徒であるというべきである。
C. 小括
以上より、音楽教室における生徒の演奏の主体は“生徒”であるから、生徒の演奏によっては、原告らは、被告らに対し、演奏権侵害に基づく損害賠償債務又は不当利得返還義務のいずれも負わないと判断しました。
6. 知財高裁判決のまとめ
知財高裁では、原審の東京地裁とは異なり、実際の演奏者(教師又は生徒)で場合分けをして検討・判断を行いました。教師による演奏では、原審と同様に“原告ら”が著作物の利用主体であると認定し、そのうえで、「公衆」及び「聞かせることを目的」への該当性を肯定しました。生徒による演奏では、原審で認定した原告らの管理・支配性を否定し、そのうえで、演奏行為の本質からみて、生徒がした演奏を原告らがした演奏とみることは困難であることから、原告ではなく“生徒”が著作物の利用主体であると認定しました。
これにより、「公衆」該当性は否定されるので(前記5.1B.参照)、生徒による演奏の場合、原告らは、被告らに対し、演奏権侵害に基づく損害賠償債務又は不当利得返還義務のいずれも負わないと判断しました。
7. さいごに
本コラムでは、音楽教室事件の知財高裁判決をご紹介しました。この判決をどう評価するかは難しいところがありますが、カラオケ法理適用の限界点を示した判決という観点では大変興味深い裁判例といえます。本件は当事者双方とも最高裁へ上告していますので、今後最高裁が本件をどのように判断するか気になるところです。