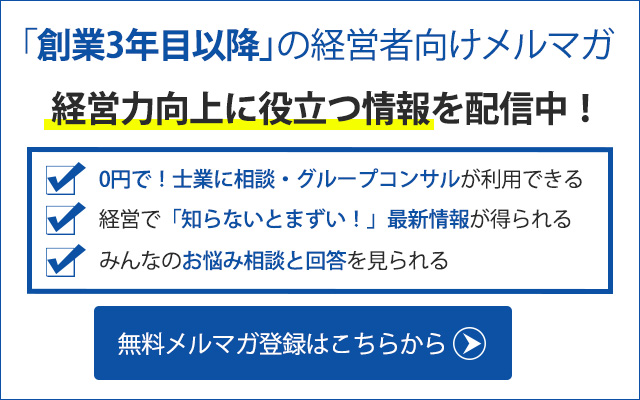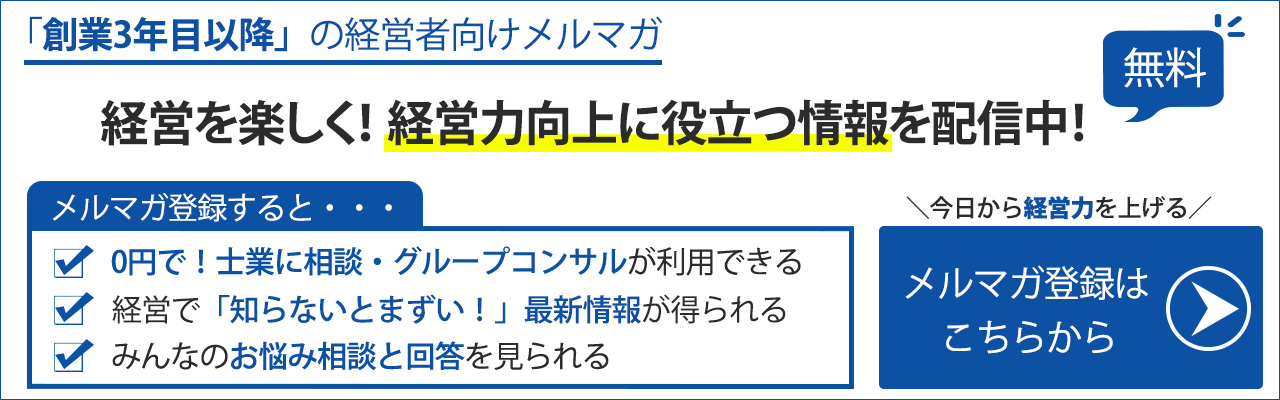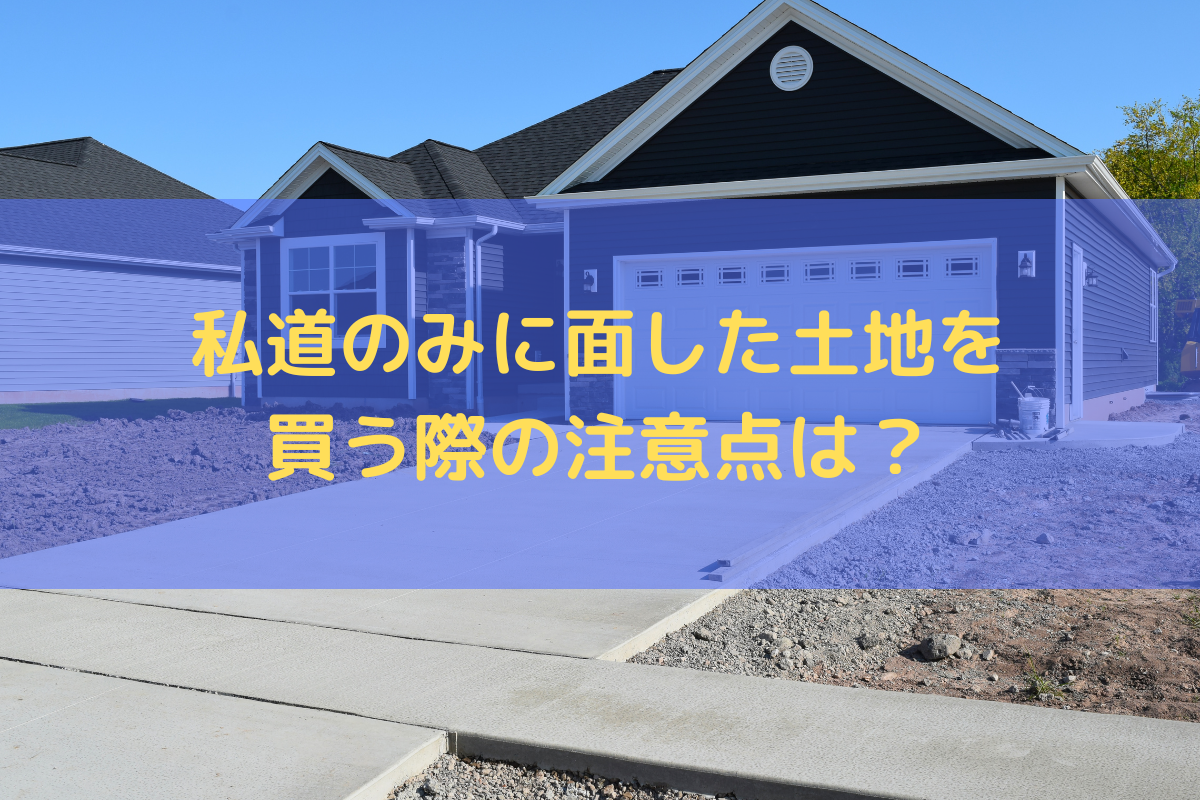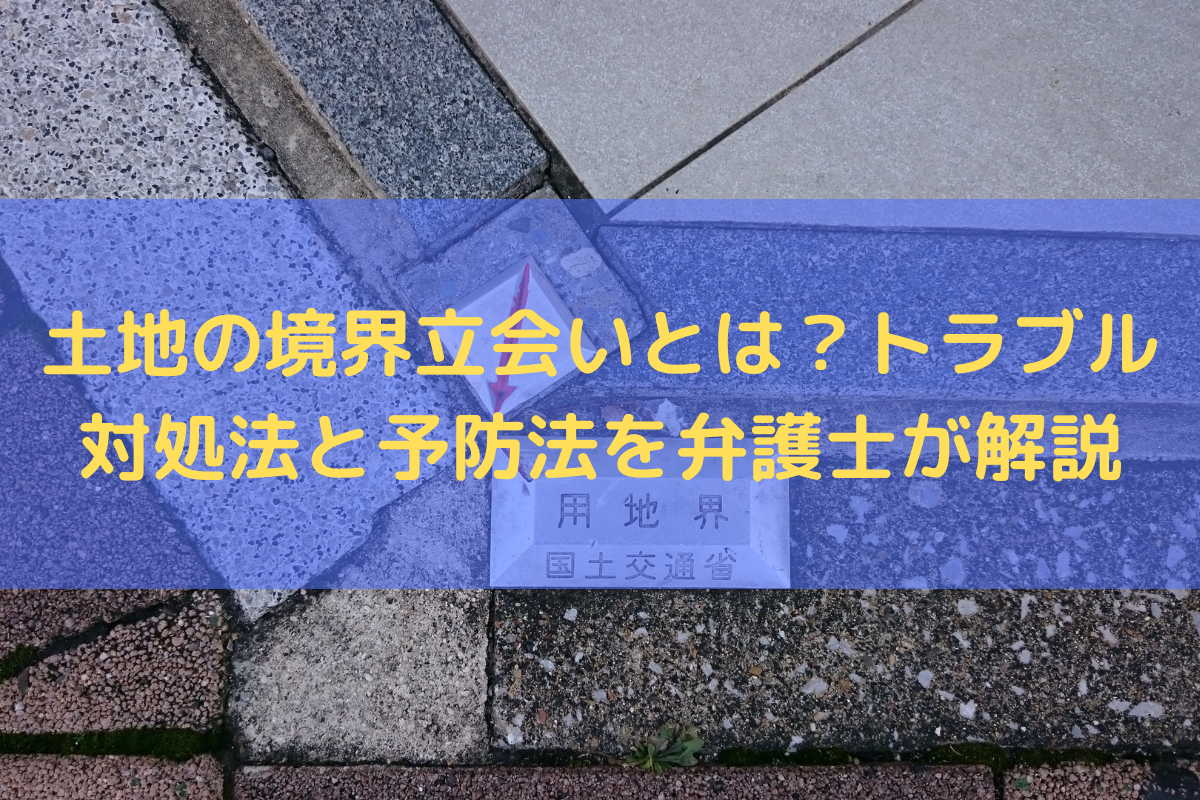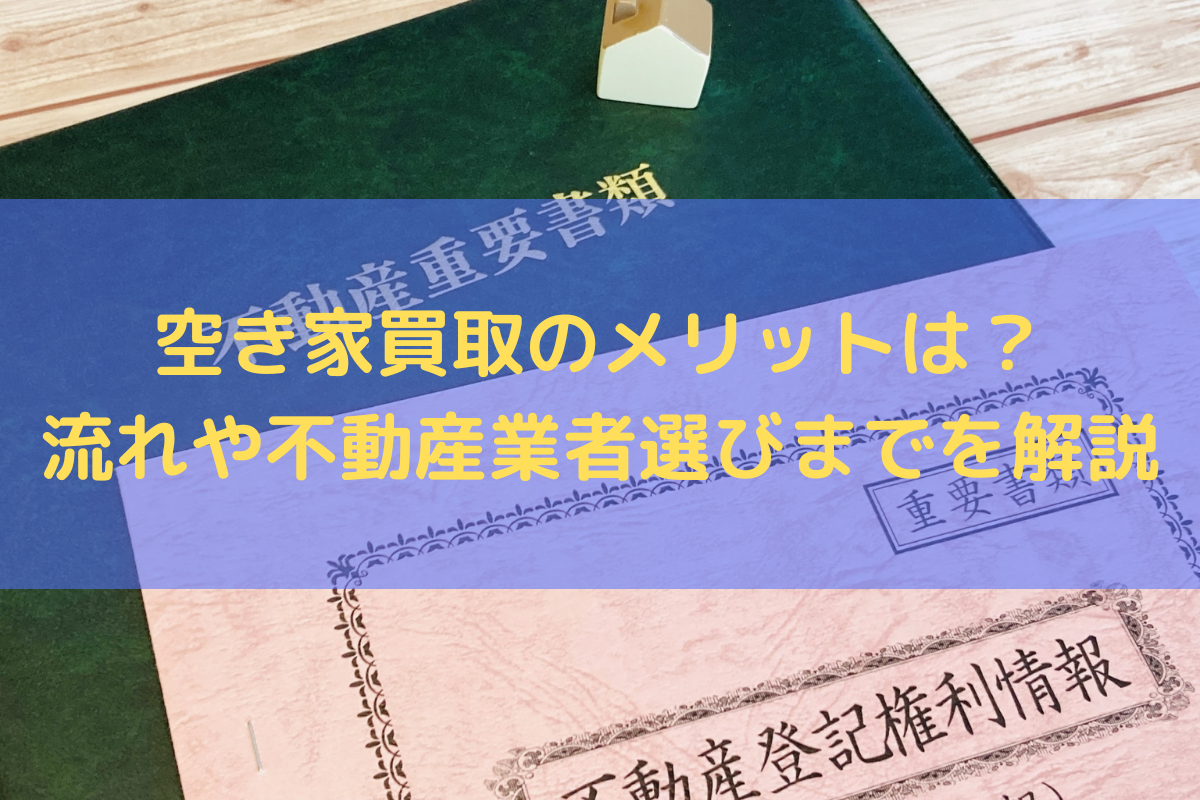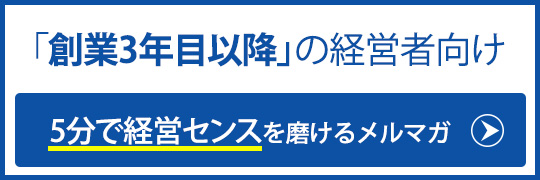共有不動産を売却する方法・手続きは?弁護士がわかりやすく解説
共有不動産を所有している場合において、この不動産全体を売却するためには、原則として共有者全員の合意が必要です。では、共有者の一部が所在不明となっている場合などには、不動産を売却する手立てはないのでしょうか?
今回は、令和5年(2023年)4月1日から施行される改正法を踏まえ、共有不動産を売却する手続きについてくわしく解説します。
目次
共有不動産とは
共有不動産とは、複数人で所有している土地や建物のことです。共有について、民法では、「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」と規定しています。
誤解の多いところですが、たとえば150㎡の土地をA、B、C3人が3分の1ずつの持分で共有している場合、それぞれが50㎡部分の権利を持っているわけではありません。A、B、Cそれぞれが150㎡の土地全体を、3分の1ずつ使用する権利を持っているということです。
土地を50㎡ずつ持っているというよりは、1年365日のうち1人あたり約121日ずつこの土地全体を利用できる権利があるというイメージが近いでしょう。また、この土地を月30万円の賃料で貸している場合には、A、B、Cそれぞれが10万円を受け取る権利があるということです。
共有不動産が生まれる理由
共有不動産は、ときにさまざまなトラブルの原因となります。
では、共有不動産はなぜ生まれてしまうのでしょうか?不動産が共有となる主な原因は、次の2つです。
不動産の共同購入
共有不動産が生まれる1つ目の原因は、不動産の共同購入です。夫婦で購入する場合のほか、親しい友人や親族同士で購入する場合などがあります。
しかし、特に友人や親族同士での購入は、後のトラブルの原因となりかねません。たとえば、共有者の一部と連絡が取れなくなり不動産の利活用に支障が出る場合や、共有者の一部の経済状況が変わったことで、共有持分を高額で買い取るよう他の共有者に請求する場合などが考えられます。
また、一部の共有者がその共有不動産を売りたいと考えていても他の共有者が売却に同意しなければ不動産全体を売ることができず、この点で争いとなる可能性もあるでしょう。
さらに、共有者の一部が亡くなりその子や配偶者などが相続すれば少し縁遠い人同士での共有となり、さらに意見の取りまとめが難しくなる可能性が高くなります。
相続
共有不動産が生まれるもう1つの原因は、相続です。
前提として、相続人の全員が納得するのであれば、遺産はどのように分けても構いません。
たとえば、長男、二男、長女の3名が相続人であるからといって必ずしも遺産を3分の1ずつにしなければならないわけではなく、3名とも納得するのであれば、たとえば二男が全財産を相続しても良いわけです。
しかし、相続人がそれぞれ自分の相続分を主張する場合において、主な遺産が不動産しかないような場合には、遺産分割は困難となります。1人だけが主な遺産である不動産を相続することは、他の相続人が納得しないためです。
また、不動産を取得した相続人に、その代わりとして他の相続人に支払うだけの金銭があれば良いのですが、それだけのお金が用意できない場合も多いでしょう。
このような場合に、苦肉の策として、不動産を相続人同士の共有にする場合があります。
これが、共有不動産が生まれる原因の1つです。
また、名義人の相続が起きた後、遺産分割協議さえしないままで不動産が放置されているケースも少なくありません。この場合には登記簿上の名義人こそ亡くなった人(「被相続人」といいます)のままであるものの、実質的には相続人全員での共有状態となっています。
共有不動産を売却する基本の方法
共有名義となっている不動産を売却したい場合、どのような方法をとれば良いのでしょうか?基本の考え方は、次のとおりです。
共有者全員の合意で売却する
共有不動産の全体を売却するためには、共有者全員の合意で売却する必要があります。たとえ1人でも売却に同意しない人がいれば、その人を無視して不動産全体を売却することはできません。
これは、たとえ100分の99の共有持分を持つ人が売却したいと考えており、100分の1のみの持分を持つ人が売却を拒否している場合も同様です。多数決や持分割合の多い人の独断などで決められるわけではありませんので、注意しましょう。
自分の持分だけを売却する
共有者の一部に売却を拒否する人や、行方不明で売却の意思を確認できない人などがいる場合であっても、自分の持分だけを売却することは可能です。
たとえば、A、B、Cの3名が3分の1ずつの共有持分を有する場合において、Cが売却を拒否している場合には、AとBの持分(全体の3分の2の共有持分)のみを売却することができます。
しかし、AとBの共有持分のみを購入したとしても、引き続きCの持分は残ります。そのため、買い手が自由な利用や転売をすることは困難でしょう。
こうした理由からそもそも買い手が見つからないリスクがあり、仮に買い手が見つかったとしても、不動産全体を売却する場合と比較して売買価値が低くなりやすい傾向にあります。
なお、例で挙げたCが売却を拒否しているのではなく所在不明で連絡が取れない状態にある場合などには、改正により誕生した制度で活路が見いだせるでしょう。これについては、この先でくわしく解説します。
共有持分を売却する4つの方法
共有不動産を売却するには、どのような方法があるのでしょうか?
ここでは、A氏、B氏、C氏の3人が不動産を共有している前提で、共有不動産を売却する4つの方法を解説します。
共有者全員で協力して売却する
1つ目であり王道ともいえるのは、共有者全員が協力して不動産を売却する方法です。
A氏、B氏、C氏の3人が協力することで、不動産を単独で所有しているのと同様の手続きで不動産を売却することが可能となります。
ただし、この場合は共有者全員で足並みをそろえることが、売却のハードルとなる可能性があります。
たとえば、A氏とB氏は「2,000万円なら売ってもよい」と考えている一方で、C氏が「2,500万円以上でないと売りたくない」と考えている場合は、売却が頓挫してしまいかねません。
そのため、共有者全員で売却を進める際は、売却条件についてあらかじめよく話し合い、全員の意見をまとめておくとよいでしょう。
他の共有者の持分を買い取って全体を売却する
2つ目は、一部の共有者が他の共有者の持分を買い取ったうえで、不動産全体を売却する方法です。
たとえば、A氏がB氏とC氏の共有持分を買い取ることで、不動産全体がA氏の単独所有となります。
その後、A氏はB氏やC氏の協力を得ることなく、自分1人の判断で売却を進めることが可能となります。
この方法は、全員で協力して不動産を売却する場合と比較して、第三者への売却をA氏が1人で進められることが最大のメリットです。
ただし、A氏がB氏やC氏から共有持分を買い取るにあたって価格の協議がまとまらず、交渉が難航する可能性はあります。
また、A氏が想定した通りの価格で不動産を第三者に売却できなかった場合、A氏1人がその損失を被ることとなるリスクがあります。
自分の持分のみを第三者に売却する
3つ目は、自分の持分のみを第三者に売却する方法です。
誤解している人も少なくありませんが、不動産は共有持分のみであっても第三者に売却することが可能です。
たとえば、A氏が自己の持分である3分の1のみを、第三者であるX氏に売却する場合などがこれに該当します。
ただし、A氏の共有持分を買い取ったX氏はその不動産をB氏やC氏と共有することとなり、自身の自由に使えるわけではありません。
そのため、一般個人が共有持分を購入することは想定しづらく、この場合の購入者となるX氏は、共有不動産の持分の買い取りを専門とする買取業者であることが多いでしょう。
なお、この場合の価格は不動産の時価に共有持分を乗じた価格で売却することはできず、非常に低額での売却となることが一般的です。
他の共有者に自分の持分を売却する
4つ目は、自身の共有持分を、他の共有者に売却する方法です。
たとえば、A氏が自身の共有持分を、B氏やC氏に売却する場合などがこれに該当します。
A氏が共有持分を売りたいと考えている一方でB氏やC氏が共有持分の売却を望んでいない場合には、これが有力な選択肢となるでしょう。
この場合は、2つ目で挙げた「他の共有者の持分を買い取って全体を売却する」と同様に、買取価格の協議がまとまらないと交渉が難航する可能性があります。
共有持分の売却にかかる費用と必要書類
共有持分の売却には、どの程度の費用がかかり、どのような書類が必要となるのでしょうか?
ここでは、共有者全員が協力して不動産を売却することを前提に、一般的にかかる費用や必要書類を紹介します。
共有持分の売却にかかる主な費用
不動産の共有持分の売却では、次の費用などがかかります。
| 費用 | 概要 |
| 不動産会社に支払う仲介手数料 | 不動産の売買契約が成立した際に、不動産会社に支払う報酬。原則として「不動産の売却価額×3%+6万円+消費税」で計算する。 |
| 印紙税 | 不動産の売買契約書に、収入印紙を貼付して納めるべき税金。
印紙税額は売却価格によって異なるものの、数千円から数万円程度であることが一般的。 |
| 抵当権(担保)の抹消費用 | 売却する不動産に抵当権が付いている場合に、これを抹消するためにかかる費用。
・登録免許税:不動産の数×1,000円 ・司法書士報酬:1万円~2万円程度 ・ローンの繰り上げ返済手数料:1万円~3万円程度 |
| 土地の測量費用 | 隣地との境界が確定されていない場合に必要となる費用。
おおむね、30万円〜80万円程度。 |
また、不動産の売却によって利益が出た場合には、別途譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税額は売却によって生じた利益の額や特例適用の可否などによって大きく異なるため、税理士などの専門家へ相談のうえ計算してもらうのがおすすめです。
共有持分の売却の一般的な必要書類
不動産の共有持分の売却では、次の書類が必要となることが一般的です。
権利証または登記識別情報
土地測量図と境界確認書
共有者全員印鑑証明書
具体的な必要書類は状況によって異なるため、売却について不動産会社に相談する際に確認することをおすすめします。
共有持分の売却で発生する主なトラブルの例と対処法
共有持分の売却では、どのようなトラブルが生じる可能性があるのでしょうか?
最後に、共有持分の売却で生じがちな主なトラブルと対処法を紹介します。
他の共有者と売却に関する意見がまとまらない
他の共有者と売却に関する意見がまとまらないと、売却が難航する可能性があります。
先ほど挙げたように、共有者のうちA氏とB氏が「2,000万円なら売ってもよい」と考えている一方で、C氏が「2,500万円以上でないと売りたくない」と考えている場合などです。
この場合は、弁護士へご相談ください。
弁護士が代わりに交渉することで、交渉がまとまる可能性があるためです。
また、それでも意見がまとまらない場合は裁判所に共有物分割調停や共有物分割訴訟を申し立てることで、解決を図ることが可能となります。
他の共有者が共有不動産買取会社に持分を売却してしまう
他の共有者が共有持分を共有不動産買取会社に売却することで、トラブルに発展する可能性があります。
共有不動産買取会社は決してボランティアで共有持分を買い取っているわけではなく、その後不動産全体を取得して全体を売却し、転売益を得ることを目的としていることが一般的です。
そのため、他の共有者が共有不動産買取会社に持分を売ってしまうと、持分を取得した共有不動産買取会社から強引な買取りを持ちかけられたり、買い取るための訴訟を提起されたりする可能性があります。
このような事態が生じた際は、早期に弁護士へご相談ください。
弁護士にご依頼頂くことで共有不動産買取会社と代理で交渉することが可能となるほか、共有不動産買取会社から違法な買取交渉をされるリスクを抑えることが可能となります。
また、このような事態を避けるため、他の共有者とは日ごろから良好な関係を築いておくことをおすすめします。
良好な関係を築いておけば、共有不動産買取会社に売却する前に、共有持分の買取りを打診してもらえる可能性が高くなるためです。
まとめ
共有不動産は共有者全員が協力して売却するのが原則ですが、ほかに共有者がその持分のみを売却する方法や、他の共有者の持分を買い取って不動産全体を売却する方法などが考えられます。
共有不動産を売却したい場合は、状況に応じた適切な売却方法を検討しましょう。
売却の進め方がわからない場合や他の共有者との話し合いがまとまらない場合などには、弁護士へ相談をおすすめします。
たきざわ法律事務所では不動産法務にまつわるリーガルサポートに力を入れており、共有不動産の売却についても多くの解決実績があります。
共有不動産の売却についてトラブルが生じている際や他の共有者と意見がまとまらずお困りの際などには、たきざわ法律事務所まで、まずはお気軽にご相談ください。