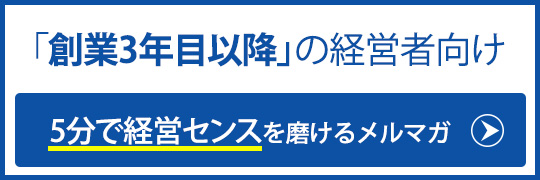【2024】ネットで誹謗中傷被害を受けたらどうする?弁護士がわかりやすく解説
誰もが簡単にインターネット上で情報を発信したり意見を投稿したりできるようになった昨今、インターネット上での誹謗中傷が社会問題となっています。
誹謗中傷の被害をインターネット上で受けたら、どうすればよいのでしょうか?
また、インターネット上での誹謗中傷には、どのような法的措置をとることができるのでしょうか?
今回は、インターネット上で誹謗中傷された場合の対応について詳しく解説します。
目次
誹謗中傷とは
誹謗中傷とは、「悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為」です。
インターネット上では、匿名であるとの思い込みや相手の顔が直接見えないことなどからか、誹謗中傷が後を絶ちません。
ネットでの誹謗中傷に関するよくある誤解
インターネット上での誹謗中傷には、誤解が少なくありません。
まずは、ネットでの誹謗中傷にまつわるよくある誤解を4つ解説します。
匿名なら特定できない
1つ目は、匿名での投稿であれば、投稿者が特定できないというものです。
確かに、匿名アカウントでの投稿であり個人を特定できる内容の投稿などをしていないのであれば、平常時には個人は特定されません。
ただし、誹謗中傷の加害者となった場合は、被害者側が発信者情報開示請求をすることで、個人(投稿に使ったプロバイダの契約者名や契約者住所など)を特定することが可能となります。
投稿者がアカウントを消したら特定できない
2つ目は、誹謗中傷の投稿をしても、その後SNSのアカウントなどを消したら個人が特定できないというものです。
しかし、実際には投稿を消したりアカウントを消したりしたからといって、発信者情報の開示が受けられなくなるわけではありません。
たとえアカウントが消えていても、あらかじめ撮影したスクリーンショットなどの証拠をもとに被害者側が発信者情報開示請求をすることで、個人を特定できる可能性があります。
ただし、投稿からあまりにも時間が経っており、プロバイダでのログの保存期間(おおむね3か月から6か月程度)を過ぎているのであれば、もはや投稿者の特定は困難です。
伏せ字にすれば罪に問われない
3つ目は、伏せ字にすれば罪に問われないというものです。
確かに、伏せ字にすることで誰もその誹謗中傷の対象者がわからないのであれば、罪に問うことは困難でしょう。
しかし、実際には伏せ字にしても周辺事情や断片的な情報から誰のことであるかわかるように書かれていることが多く、その場合は伏せ字にしたことだけを理由として免責されるものではありません。
また、誰のことであるかがすべての人にとって分かる必要はなく、同じ会社など近しい人が見たときに誰のことであるか分かる程度であれば、罪に問われる可能性があります。
本当のことなら罪に問われない
4つ目は、本当のことであれば罪に問われないというものです。
刑法上の名誉毀損罪には違法性阻却事由が設けられており、たとえ他者を名誉毀損した場合であっても、次のすべてに該当するのであれば違法性は阻却されます。
- 公共性の利害に関する事実であること
- その目的が専ら公益を図る目的であること
- 真実であることの証明があったこと又は真実であると信ずるについて相当の理由があること
しかし、真実であることはこのうち一つの要件でしかありません。
つまり、たとえ真実であったとしても公共性がなかったり単なる嫌がらせ目的であったりする場合は、違法性は阻却されません。
「本当のことなら何を書いてもよい」というわけではないことには注意してください。
インターネットで誹謗中傷の被害に遭った場合の初期対応
インターネット上で誹謗中傷の被害に遭った場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
ここでは、誹謗中傷された場合の初期対応について解説します。
なお、誹謗中傷について法的措置がとれるのは一般個人だけではなく、企業や医院などであっても可能です。
誹謗中傷の被害に遭ってお困りの際は、たきざわ法律事務所までご相談ください。
スクリーンショットで証拠を残す
インターネット上で自身を誹謗中傷する投稿を見つけたら、その場で証拠を残すことをおすすめします。
なぜなら、その後誹謗中傷に対して法的措置をとる際には証拠が必要となりますが、法的措置を予見した投稿者が投稿やアカウントを消してしまう可能性があるためです。
投稿の証拠は、スクリーンショットの撮影で残すことが一般的です。
スクリーンショットは、次の内容が漏れなく掲載されるように撮影してください。
- 誹謗中傷投稿の内容
- 誹謗中傷投稿に関連する前後のやり取り
- 誹謗中傷投稿のURL
- 誹謗中傷投稿の日時
撮影は、可能な限りスマートフォンではなく、パソコンから行うことをおすすめします。
なぜなら、スマートフォンからの撮影では、URLなどの表記が不完全となりやすいためです。
また、誹謗中傷の投稿がされた場所(Xなのか、インターネット掲示板なのか、Googleの口コミなのか)などによって、スクリーンショットを撮るべき箇所も変わります。
具体的には、弁護士へご相談ください。
相手に直接言い返さない
インターネット上で誹謗中傷がなされた場合、言い返したくなることもあるでしょう。
特に、事実と異なる内容を投稿された場合はなおさらです。
しかし、自身を誹謗中傷している相手に直接言い返すことは、おすすめできません。
なぜなら、直接言い返せば相手がヒートアップして、誹謗中傷がエスカレートするおそれがあるためです。
また、言い返した内容によっては相手から反対に誹謗中傷であるなどとして法的措置を取られる可能性があるほか、法的措置をとるにあたって不利となるおそれもあります。
早期に弁護士へ相談する
誹謗中傷投稿のスクリーンショットを撮影したら、できるだけ早期に弁護士へ相談してください。
早期に相談をおすすめする理由は、投稿者を特定するための発信者情報開示請求は、時間との勝負であるといっても過言ではないためです。
大前提として、たとえ開示が相当であると裁判所に判断されても、開示すべき情報をプロバイダが有していなければ、開示を受けようがありません。
そして、プロバイダでの情報(ログ)の保存期間はプロバイダによって異なるものの、3か月から6か月程度であることが一般的です。
そのため、この期限から逆算して、これに間に合うように手続きを進める必要があります。
また、インターネット上でなされた誹謗中傷への法的措置を自分で講じることは、容易ではありません。
無理に自分で法的措置をとろうとすると予想以上に時間がかかってログの保存期間を超過してしまうおそれがあるほか、多くの手間と時間を要してしまう可能性があります。
そのため、誹謗中傷への法的措置は、弁護士へご相談ください。
インターネット上での誹謗中傷にとり得る主な法的措置
インターネット上での誹謗中傷には、どのような法的措置をとることができるのでしょうか?
ここでは、主な法的措置を3つ解説します。
なお、これらは、いずれか1つを選択するという性質のものではありません。
まず、発信者情報開示請求は、損害賠償請求や刑事告訴の前段階として行うことが一般的です。
相手の身元がわからなければ、損害賠償請求や刑事告訴をすることが難しいためです。
また、損害賠償請求と刑事告訴は、両方の要件を満たすのであれば、両方の措置をとっても構いません。
ただし、両方の措置をとるとより時間がかかるうえ、費用もかさみやすくなります。
そのため、いずれか一方の措置をとるのか両方の措置をとるのかは、弁護士へ相談したうえで決めることをおすすめします。
削除請求
削除請求とは、誹謗中傷の投稿を削除するよう求めることです。
誹謗中傷の内容によっては、多くの人の目に触れる前に消して欲しいと考えることでしょう。
その投稿がサイトやSNSのガイドラインに違反している場合、サイトやSNSの運営者に削除を求めることで、削除が受けられる可能性があります。
また、サイトやSNSの運営者が削除に応じない場合であっても、裁判上の手続きをとることで削除が認められることもあります。
しかし、焦って削除請求をすることはおすすめできません。
なぜなら、投稿の削除はすなわち、誹謗中傷の証拠が消えてしまうことであるためです。
また、単に削除をしただけでは、また同様の書き込みがなされ、いたちごっことなる可能性もあります。
そのため、削除請求をするのであれば、投稿の証拠を残して弁護士に確認してもらってから、弁護士に相談したうえで行うことをおすすめします。
発信者情報開示請求
発信者情報開示請求とは、権利侵害情報が匿名で発信された場合に、被害者がプロバイダに対して、発信者の特定に資する情報(発信者情報)の開示を請求することを可能にするものとして、プロバイダ責任制限法で定められているものをいいます。
発信者情報開示請求は、次の2段階で行うことが一般的です。
- 誹謗中傷の舞台となったSNSやインターネット掲示板などのサービスを提供するコンテンツプロバイダ(サイト管理者)に開示請求をして、投稿のIPアドレスなどの開示を受ける
- 「1」で得た情報をもとに、投稿者が接続に使ったアクセスプロバイダに開示請求をして、プロバイダ契約者の氏名や住所の開示を受ける
しかし、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダに対して直接開示を求めても、応じてもらえる可能性はほとんどありません。
そのため、発信者情報開示請求は、裁判上の手続きによって行うことが一般的です。
なお、発信者情報の開示などについて定めたプロバイダ制限責任法が改正され、先ほど挙げた「1」と「2」の手続きをまとめて行うことができる「発信者情報開示命令に関する裁判手続」が新設されています。
従来の手続きをとることと新設された発信者情報開示命令の手続きをとることのいずれが適しているかは状況によって異なるため、弁護士へご相談ください。
損害賠償請求
損害賠償請求とは、相手の不法行為によって生じた損害や精神的な苦痛を賠償する金銭を支払うよう、相手に対して請求することです。
損害賠償請求のゴール地点は、誹謗中傷の投稿者から賠償金を受け取ることです。
損害賠償請求はいきなり裁判上で申し立てるのではなく、まず弁護士から相手に対して文書を送るなどして裁判外で行うことが一般的です。
この時点で相手が誹謗中傷を認めて謝罪をし、請求に応じた場合は、この時点で示談が成立して事件が解決します。
一方、相手方が請求を無視するなど不誠実な対応をする場合は、裁判へと移行して損害賠償請求をすることとなります。
刑事告訴
刑事告訴とは、警察などの捜査機関に対して犯罪行為の事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
刑事告訴のゴール地点は、誹謗中傷の投稿者が処罰を受けることです。
誹謗中傷はその内容に応じて、刑法上の名誉毀損罪や侮辱罪などに該当する可能性があります。
これらはいずれも「親告罪」とされており、相手を刑事裁判にかけるためには、被害者からの告訴がなければなりません。
告訴状が受理されると警察で捜査がなされ、必要に応じて相手が逮捕されます。
その後は検察に身柄が送られ、さらに検察でも捜査がなされたうえで、起訴か不起訴かが決まります。
起訴とはその事件について刑事裁判にかけることであり、不起訴とは刑事裁判にかけず罪を不問とすることです。
起訴がされると刑事裁判が開始され、有罪・無罪や量刑が決まります。
ただし、誹謗中傷事件では不起訴となる可能性も低くないうえ、たとえ起訴されても執行猶予付きの判決となることが少なくありません。
執行猶予とは、刑の執行を一定期間猶予し、その間に罪を犯さなかった場合に刑罰権を消滅させる制度です。
そのため、刑事告訴までをするかどうかは、弁護士へ相談したうえで慎重に検討すると良いでしょう。
まとめ
インターネット上で誹謗中傷をされたら、相手に対して法的措置がとれる可能性があります。
たとえば、損害賠償請求や刑事告訴などです。
また、投稿者が匿名であっても諦める必要はありません。
相手が匿名であったとしても、発信者情報開示請求をすることで、身元を特定できる可能性が高いためです。
しかし、ログは永久に保存されるわけではなく、相手に法的措置を講じるためには、ログの保存期間内に発信者情報開示請求を行う必要があります。
そのため、インターネット上で誹謗中傷に被害に遭ったらその場で証拠を残したうえで、できるだけ早期に弁護士へご相談ください。
たきざわ法律事務所ではインターネット上での誹謗中傷への対応に力を入れており、発信者情報の開示についても多くの成功実績がございます。
インターネット上で誹謗中傷の被害に遭ってお困りの際は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。