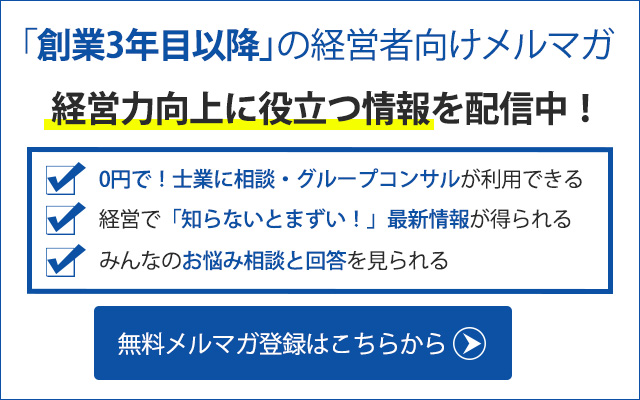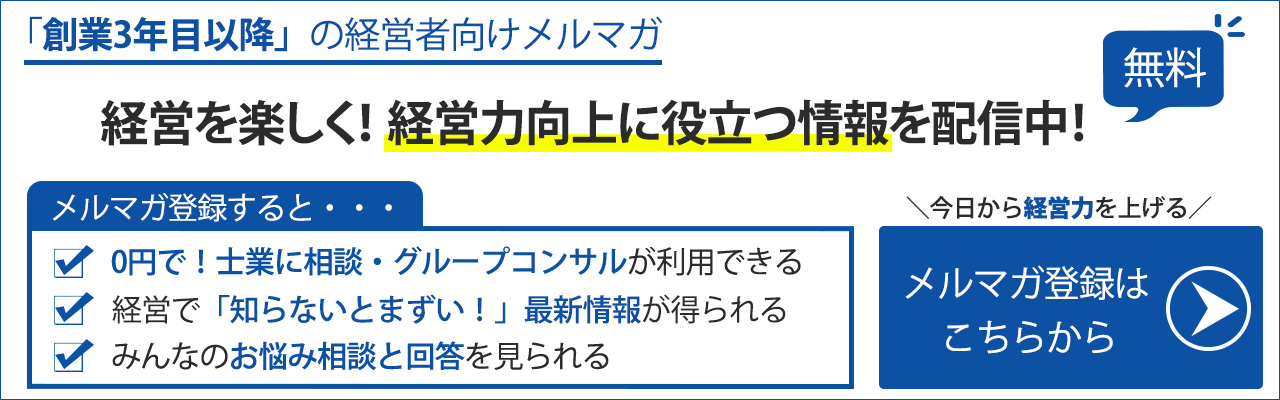【比較】土地は「生前贈与」と「相続」のどちらが得?親名義の土地を子へ渡すには
親名義となっている土地を子に移転したい場合、「生前贈与」で渡すのと「相続」で渡すのでは、どちらが得なのでしょうか?今回は、生前贈与と相続について、かかる費用や実際に行う際のポイントを弁護士が徹底比較して解説します。
目次
生前贈与と相続とは

はじめに、生前贈与と相続について、定義を確認しておきましょう。
生前贈与とは
生前贈与とは、所有者が存命のうちに他者へ財産を無償で引き渡すことです。この記事でいえば、親が存命のうちに土地の名義を子に変えることを指します。
厳密にいえば、単に「贈与」といった場合には、生前贈与のほかに死因贈与も含まれます。
死因贈与とは、亡くなったことを機に効力が発生する贈与のことで、税務上は相続で渡した場合と同じように取り扱われますので、生前贈与とは区別して考えるべきでしょう。
生前贈与をするためには、お互いの「あげます」「もらいます」の意思の合致が必要です。そのため、親が重い認知症などとなり意思疎通がはかれない状態となった場合には、もはや生前贈与をすることはできません。
生前贈与で財産をもらった場合には、原則として贈与税の対象となります。
相続とは
相続とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の財産を、子などの相続人が引き継ぐことを指します。
元々の名義人が亡くなっている以上は、「あげます」という意思表示を受けることはもはや不可能です。そのため、被相続人が生前にのこした遺言書か、相続人全員の話し合いである遺産分割協議で誰がどの財産を引き継ぐかを決めることとなります。
相続で財産をもらった場合には、原則として相続税の対象となります。
土地を生前贈与した場合にかかる税金

親名義の土地を生前贈与で子に移転した場合には、原則として次の税金の対象となります。それぞれ、概要を解説しましょう。
贈与税
生前贈与にかかる代表的な税金は、贈与税です。
贈与税は1件1件の贈与に対して個別でかかるわけではなく、その年1月1日から12月31日までの間に、贈与を受けた人(「受贈者」といいます)が受けたトータルの贈与額に対して課税されます。
この、トータルの贈与税額から110万円という基礎控除額を引き、残った額を税率表にあてはめて税額を計算します。
仮に、18歳以上の者が評価額3,000万円の土地を親から生前贈与でもらった場合、その年に他の贈与をまったく受けていないと仮定すると、かかる贈与税は次のとおりです。
- 贈与税額=(3,000万円-110万円)×45%-265万円=1,035万5,000円
これだけの額を、原則として現金一括払いにて納める必要があります。
登録免許税
登録免許税とは、土地や建物などの不動産の名義変更をする際に、法務局で支払うべき税金です。生前贈与の場合の登録免許税額は、原則として次のように計算します。
登録免許税額(贈与)=不動産の固定資産税評価額×1,000分の20
たとえば、生前贈与を受けた土地の固定資産税評価額が2,500万円である場合の登録免許税額は、50万円(=2,500万円×20/1000)です。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地などの不動産を取得した人が、取得した際に支払うべき税金です。宅地である土地を令和6年3月31日までに取得した場合、不動産取得税は原則として次のように計算します。
土地の不動産取得税=土地の固定資産税評価額×2分の1×3%
たとえば、生前贈与を受けた土地の固定資産税評価額が2,500万円である場合、不動産取得税額は37万5,000円です。
毎年の固定資産税と都市計画税
固定資産税や土地計画税とは、土地や建物を持っている人が毎年支払うべき税金です。毎年、1月1日時点の所有者に対して課税がされます。
土地の生前贈与を受けた場合には、その後毎年固定資産税や都市計画税を支払うべきこととなる点にも注意しましょう。
固定資産税や都市計画税は、よほど大幅な地価変動がない限り、これまで贈与者である親が支払ってきた固定資産税や都市計画税と同程度となります。
土地を生前贈与で移転する場合のポイント

土地を生前贈与で移転する場合には、次の点に注意しましょう。
かかる税金をあらかじめトータルで試算する
何ら対策をしないまま、土地のような高価な財産を贈与してしまうと、かなり高額な税金が課される可能性が高くなります。贈与してから慌ててしまうことのないよう、贈与前に必ず、かかる税金をトータルで試算しておきましょう。
相続時精算課税制度の活用を検討する
相続時精算課税制度とは、平たくいえば「相続税で生前贈与ができる制度」です。
土地など高価な資産を移転した場合の税金は、相続税よりも贈与税のほうが高額となることが少なくありません。そのため、生前に贈与をしたい事情があるにもかかわらず、贈与税がハードルとなって生前贈与をためらう場合もあるでしょう。
そのような際に活用を検討したいのが、相続時精算課税制度です。
相続時精算課税制度を選択することにより、以後の贈与が累計2,500万円まで非課税となります。また、累計2,500万円を超えた分も、一律20%という比較的低い税率での課税となります。
ただし、相続時精算課税制度を使って贈与を受けた財産は、すべて贈与者の相続税の計算において足し戻され、相続税の対象となる点に注意が必要です。
他にも相続時精算課税制度には注意点が多いため、自己判断で選択をするのではなく、専門家に相談をしてよく理解をしたうえで選択するようにしましょう。
小規模宅地等の特例は活用できないことを知っておく
小規模宅地等の特例とは、要件を満たすことにより、相続税を計算する際に土地を最大8割減で評価することができる特例です。
非常に減税効果の高い特例ですが、この特例が適用できるのは、相続で土地を移転した場合のみです。生前贈与で土地を移転した場合には使うことができないことには注意が必要です。
他の子との不平等に注意する
子が複数いるにもかかわらず一部の子にのみ土地を生前贈与する場合には、他の子との不平等に注意しましょう。
たとえば、親にとってほぼ唯一の資産である土地を贈与する場合には、後の相続でトラブルの原因となる可能性があります。
子など、一部の相続人には、相続での最低限の取り分である遺留分が保証されています。遺留分については後ほど改めて解説しますが、生前贈与であるからといって、必ずしも遺留分から除外されるわけではありません。
生前贈与が遺留分の対象となるかどうかについては個別事情によっても異なりますので、お困りの際には弁護士へ相談することをおすすめします。
土地を相続した場合にかかる税金

親が亡くなったことに起因して、子が土地を相続した場合には、次の税金の対象となります。なお、生前贈与とは異なり、不動産取得税は課税されません。
相続税
相続税とは、相続財産全体に過去の一定の贈与財産を加算した総額(「課税価格の合計額」といいます)についてかかる税金です。相続税は、「土地にいくら」「預貯金いくら」などと個別で計算されるわけではなく、遺産全体に対して課税されます。
相続税には次の基礎控除額が定められており、そもそも課税価格の合計額がこの基礎控除額以下である場合には、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
基礎控除額が大きいため、土地などの価値の高い財産を移転する場合には、相続税の方が低くなる場合が多いでしょう。ただし、遺産の内容や相続人の状況などにより一概にいえるものではありませんので、状況に応じて個別で試算をしてもらうことをおすすめします。
登録免許税
相続で土地をもらった際にも、生前贈与の場合と同じく、登録免許税の対象となります。ただし、相続の場合の登録免許税は原則として次のように計算することとなっており、生前贈与の場合よりも税率が低くなっています。
登録免許税額(相続)=不動産の固定資産税評価額×1,000分の4
たとえば、相続で取得した土地の固定資産税評価額が2,500万円である場合の登録免許税額は、10万円です。
毎年の固定資産税と都市計画税
相続で土地を取得した場合であっても、以後毎年の固定資産税と都市計画税は課税されます。
ただし、生前贈与で土地をもらった場合と比較すると、相続が起きるまでは親が固定資産税や登録免許税を支払ってきていますので、この点でトータルの支払い額には差が生じるでしょう。
土地を相続で移転する場合のポイント

土地を相続で移転する場合には、次の点に注意しましょう。
遺言書を作成しておく
ある土地を特定の子に相続させたい場合には、親があらかじめ遺言書を作成しておきましょう。仮に遺言書がなければ、相続人全員で話し合いをして誰がその土地を相続するのかを決めることとなるためです。
話し合いにおいて、他にもその土地を欲しいと主張する相続人がいれば、元々土地を渡したいと考えていた子が土地を受け取れない可能性があります。
他の相続人の遺留分に注意する
土地を特定の子に相続させる遺言書を作成する場合には、他の相続人の遺留分に注意しましょう。
遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での取り分のことです。
遺留分を侵害した遺言書も有効ではあるものの、遺留分を侵害された相続人から財産を多く受け取った者に対して、侵害した遺留分相当の金銭を支払ってくれと請求される可能性があります。
具体的に見ていきましょう。
子の遺留分は、本来の法定相続分の2分の1です。たとえば、長男と二男の2名のみが法定相続人である場合、それぞれの遺留分は4分の1(=2分の1×2分の1)となります。仮に遺産総額が4,000万円であるのであれば、長男と二男の遺留分はそれぞれ1,000万円です。
この場合に、遺産の大半を占める評価額3,500万円の土地建物を長男に相続させるとの遺言書を作成してしまうと、残りの遺産は500万円(=4,000万円-3,500万円)しかありません。これをすべて二男が相続したとしても、二男の遺留分にはまだ500万円(=1,000万円-500万円)不足してしまいます。
この場合、二男は長男に対して侵害された遺留分相当の500万円を金銭で支払うよう請求することが可能です。これを、「遺留分侵害額請求」といいます。
このような請求がなされるとトラブルになる可能性がありますので、遺言書を作成する際には、他の相続人の遺留分に配慮しつつ作成するようにしましょう。
小規模宅地等の特例の要件を確認しておく
小規模宅地等の特例とは、土地を最大8割減で評価することができる相続税の特例です。非常に減税効果の高い特例ですが、特例の適用には複雑な要件があります。
たとえば、配偶者が存命であるにもかかわらず、別居の子が土地を相続した場合には、小規模宅地等の特例を使うことはできません。相続税がかかりそうな場合には、小規模宅地等の特例の適用要件にも注意しつつ、土地を相続させる相手を検討すると良いでしょう。
相続登記まで速やかに済ませておく
土地を相続したら、法務局での相続登記までを速やかに済ませておきましょう。せっかく自分が相続できることとなったとしても、相続登記をしないままでいると、その間に他の相続人の債権者などが土地の持分を差し押さえ、売却してしまうかもしれません。
そのような事態となれば、土地を取り戻すことは困難です。余計なトラブルに発展させないよう、相続登記まで速やかに済ませておくことをおすすめします。
土地は生前贈与と相続のどちらが得?

結局のところ、親から子への土地の移転は、生前贈与と相続のどちらが得なのでしょうか?
一般的には、税金面のみを見れば、相続の方が低く済むことが多いでしょう。ただし、これに相続人の数や資産状況などによって異なるうえ、相続時精算課税制度を使うという選択肢もあります。
また、生前贈与と相続にはそれぞれ注意点があるうえ、そもそも何のために子に土地を渡したいのかという目的によっても、最適な方法は異なるでしょう。
そのため、トータルで見ればケースバイケースであると言わざるを得ません。個別事情によるところが大きいため、土地を生前贈与で渡すか相続で渡すのかに迷ったら、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
土地は生前贈与と相続のどちらが得なのかは、非常に悩ましい問題です。
本文でも記載をしたとおり、結局のところは個別事情によるところが大きいため、弁護士や税理士などの専門家をうまく活用しつつ、自分にとって最良の方法を見つけるべきでしょう。
たきざわ法律事務所では、生前贈与や相続に関するご相談を数多くお受けしております。
土地の生前贈与や相続でお困りの際には、ぜひたきざわ法律事務所までご相談ください。