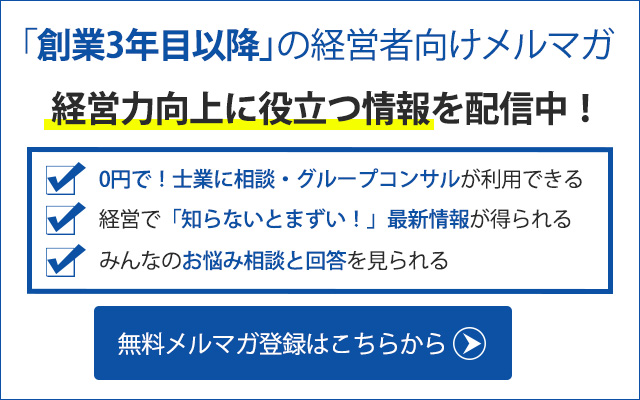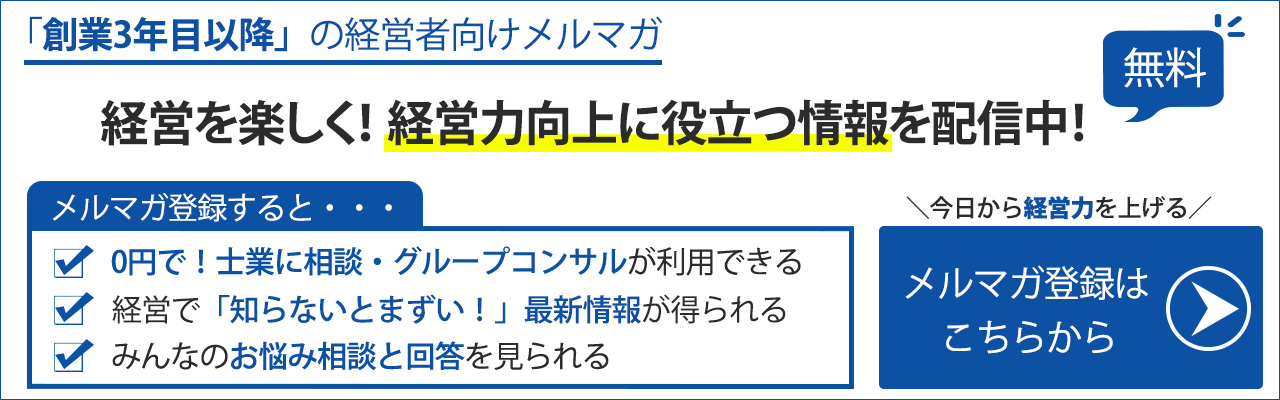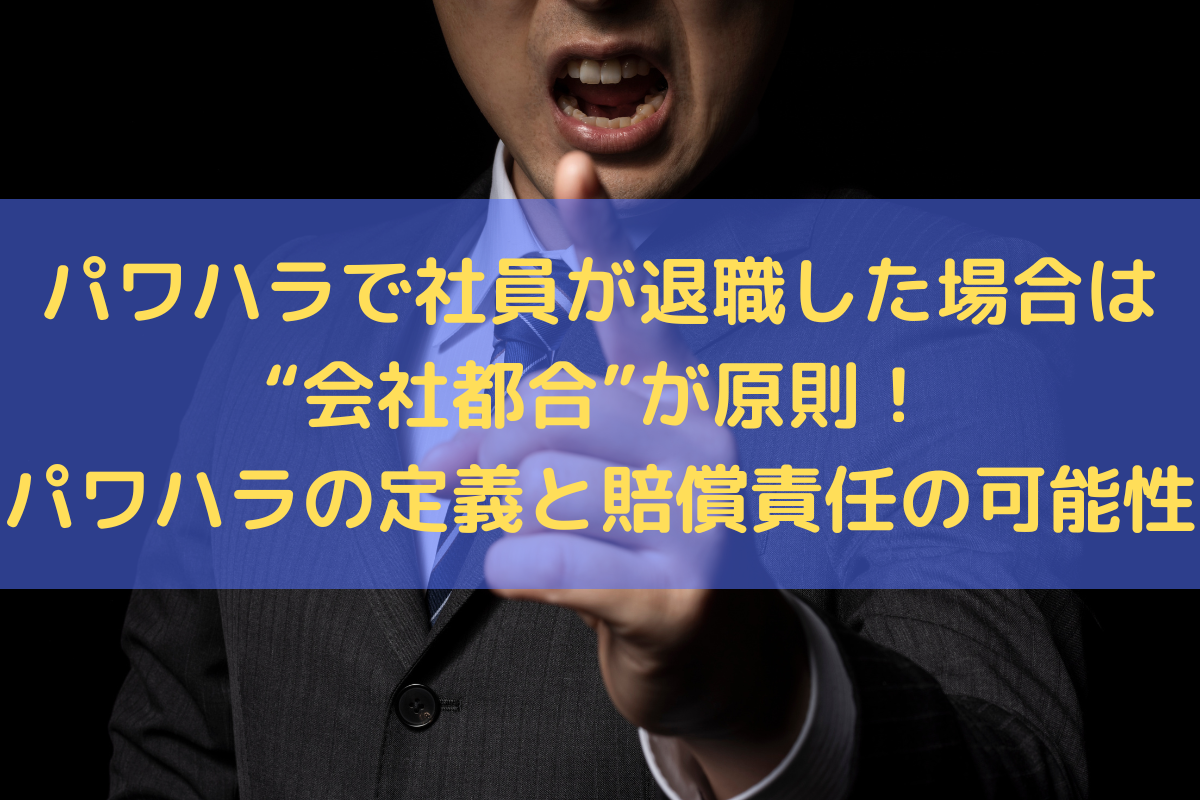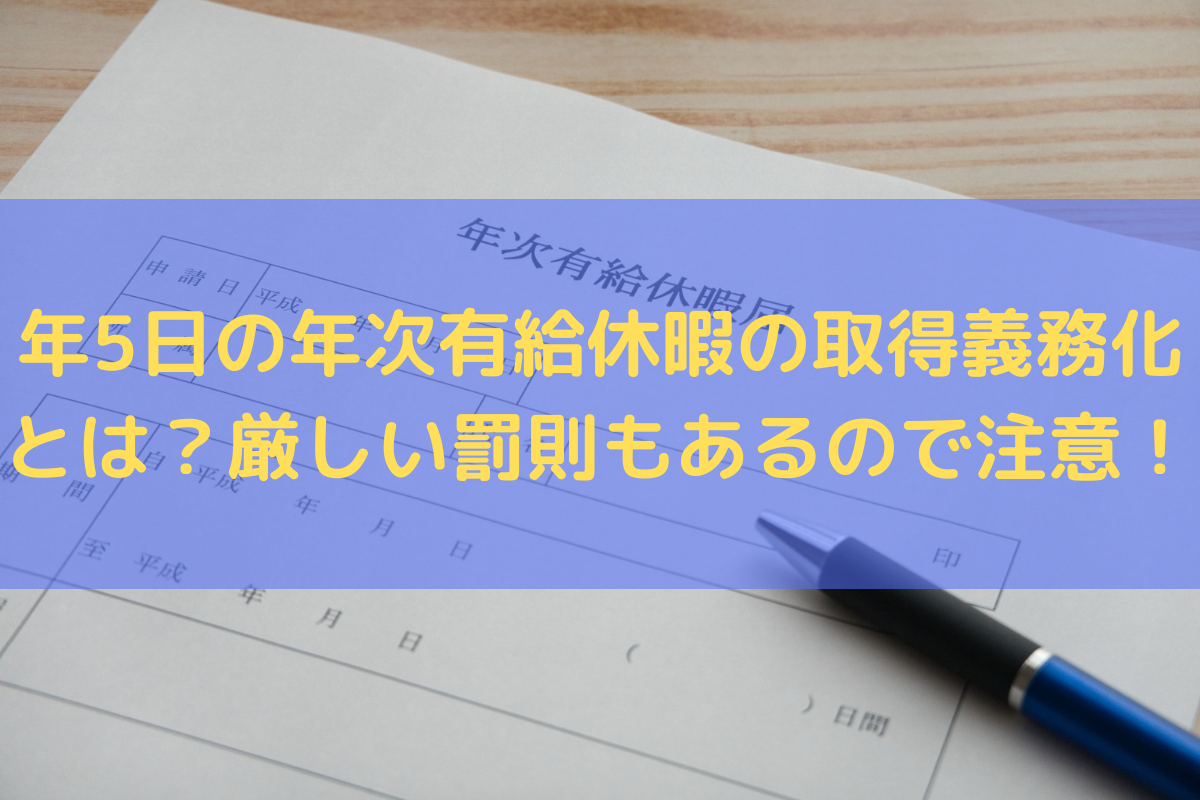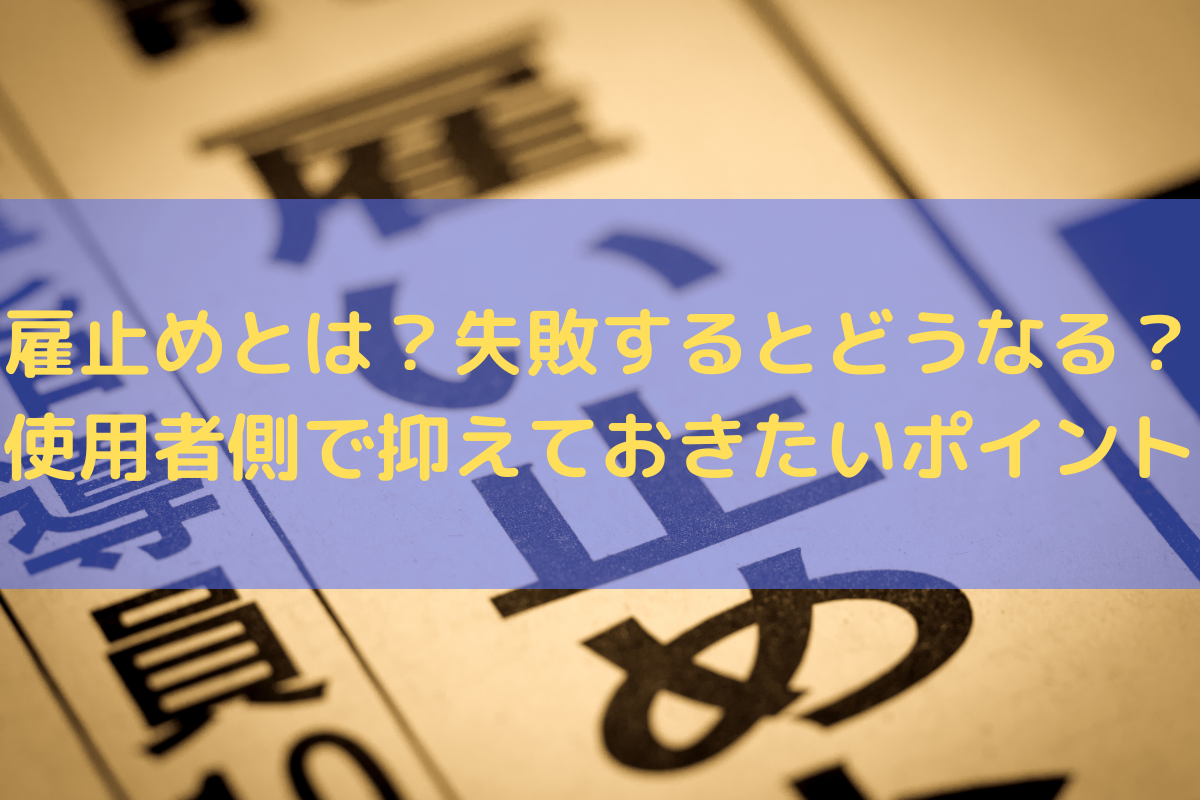有給休暇とは?制度の基礎から義務化の影響までを解説
有休、または有給休暇は、正式には「年次有給休暇」という賃金が支払われる休暇日のことです。「労働基準法」によって、一定の条件を満たした従業員に対しては毎年、有給休暇を付与することが義務付けられています。
本稿では、有給休暇の制度の基本からはじめ、ケースごとの細かいルールの解説、そして2019年4月から開始した有給休暇取得の義務化による影響など、最近の事情までを網羅して解説していきます。
目次
有給休暇は誰に付与される?
まず、有給休暇は以下の条件を満たす全労働者に付与されます。
- 雇い入れの日から6ヶ月間、継続勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
「継続勤務」とはその事業所への在籍期間を指します。そして出勤率の計算方法は、「出勤日数 ÷ 全労働日」となっています。
ポイント1:出勤日の条件
ここでの注意点は、出勤日数には以下の日も含まれることです。
- 遅刻早退した日
- 労災による療養日
- 雇用主の責任による休日
- 出産休暇
- 育児休業
- 介護休業
その日に少しでも出勤していれば有給休暇付与のための出勤日に加算されますし、出産や育児にかかる休暇を取得しても出勤日に加算されることになります。
ポイント2:全労働者に付与される
有給休暇の付与対象は「全労働者」です。有給休暇を取得できるのは正社員だけではありません。上記の条件を満たす、契約社員・パート・アルバイトなどにも有給を付与することが、労働基準法第39条で義務付けられています。ただしその量は、次に解説する通り多少異なる場合があります。
有給休暇は何日分付与される?
有給休暇の付与対象は非常に広範ですが、その日数は労働者の雇用形態や状況、勤続年数に応じて変動します。どのような条件で変動するのか見てみましょう。
有給休暇は、基本的には以下のルールで付与されます。
| 継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
| 付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
見て分かる通り、雇い入れ日から数えて6ヶ月後を目処に、1年経つ毎に少しずつ日数が増えていきます。
ただし勤務時間の少ない労働者には、それに応じたより少ない有給休暇が付与されます。1週間の所定労働日数が4日以下で、所定労働時間が30時間未満(例:週3回、各5時間のパートタイム勤務)の労働者には、以下のルールで有給休暇が付与されます。
| 所定労働日数 | 勤務継続年数 | ||||||
| 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |
| 週4日、または年169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 週3日、または年121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 週2日、または73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 週1日、または48~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※年の所定労働日数は、週ごとの労働日数が定められていない場合の基準。
労働日数が少なくなるほど、有給休暇の付与日数も減っていく仕組みになっています。
ただし、これはあくまで労働基準法に定められた有給休暇付与日数の最低値です。
少なくともこれだけの日数は付与しなければなりませんが、各事業者での取り決めとして、これより多くの有給を付与することは問題ありません。
有給休暇は使わないと消える
せっかく毎年付与される有給休暇ですが、これには2年間の有効期限があります。使わないと消えてしまうのです。
この条件は労働基準法第115条に「この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。」という文章で規定されています。
有給休暇に有効期限があることは有名ですが、その根拠は雇用主の都合ではなく労働基準法に規定された法律なのです。
午前休や午後休、時間休
会社によっては、午前休や午後休、時間休を取得できることがあります。これにはどのような法的根拠があるのでしょうか?
有給休暇は、原則として1日単位で取得することになっています。それよりも細かい単位で有給休暇を取得したい場合、法律には特に規定がないため、労使協定もしくは雇用者と労働者の間で合意を取る必要があります。労使協定を結ぶ場合には一般に、以下のような内容が記載されます。
誰が取得できるのか
1日より細かい単位での有給休暇の取得は、法律上の権利ではありません。よって労使双方の協議結果に従って取得できる労働者を制限することができます。
例:「継続勤務年数が2年未満の労働者は取得できない」など
有給休暇のうち何日分を取得できるのか
こちらも上記と同様の理由で、任意の内容を規定することができます。
例:「年に5日分までは時間単位で取得することができる」など
有給休暇1日は、何時間分の時間休に相当するか
こちらは一般的には1日の労働時間に相当することになるでしょう。しかし、協議次第で変更可能という点には注意してください。
有給休暇の取得時期は雇用主が変更できることがある
有給休暇は基本的に労働者の自由に取得することができますが、ある条件下においては雇用主から取得時期を変更することもできます。これが時季変更権と呼ばれる雇用主の権利です。
たとえば全ての労働者が繁忙期に有給休暇を申請すると、事業が破綻してしまいます。このようなケースにおいてのみ、雇用主には有給休暇の取得時期を変更できる権利が与えられているのです。
年次有給休暇の買い取りは義務ではない
労働基準法では、原則として有給休暇の買い取りは認めていません。よって、買い取りを条件に労働者の有給休暇の取得を妨げるのは労働基準法違反となってしまいます。
ただし、以下の条件を満たす有給休暇は買い取りができるとされています。
- 法定基準を上回る、会社が独自に付与した有給休暇
- 時効となる有給休暇
- 退職によって無効になる有給休暇
有給休暇の買い取りは、雇用主の義務ではありません。たとえば退職時に余った有給休暇の買い取りを要求されても、応じる義務はありません。ただし、退職者が残日数分の有給休暇の取得を要求した場合は、応じる必要がありますので注意が必要です。
有給休暇取得の義務化
2019年4月に、働き方改革の一環として労働基準法が改正された結果、有給休暇の取得が義務化されました。ここでは、どのような変更点があったのか整理していきます。
義務化の対象者は全員ではない
まず、有給休暇取得の義務化は、有給休暇を付与された労働者のうち、年に10日以上付与されている労働者に限定されます。これに含まれるのは以下の労働者です。
- 週5日以上、または週に30時間以上働いている
- 週4日勤務で、3.5年以上働いている
- 週3日勤務で、5.5年以上働いている
※週ごとの所定労働日数の取り決めがない場合、年単位での基準日数を適用します。詳しくは前述の表を参照してください。
1年に5日分の取得が義務化
上記の条件を満たす労働者は、毎年5日分の有給休暇を取得することが義務化されました。これまでは特に規定がなかったため、有給休暇は労働者が自由に取得してよいものでしたが、今回の改正により、必ず取らせなければいけないものとなりました。これに違反すると、雇用主に対して労働者1名につき30万円以下の罰金が課せられます。
罰金の単位が、有給休暇の取得義務に違反した労働者1名につき30万円以下であることには注意が必要です。もし10名の労働者が取得義務を満たしていなかった場合、最大300万円の罰金が課せられる可能性があります。
有給休暇の取得率を向上したい
日本全体を見た時、有給休暇の取得率は消して高くないというのが現実です。
世界の大手総合旅行ブランドの一つであるエクスペディアが毎年実施している有給休暇の国際比較調査では、日本の有給休暇消化率はほぼ一貫して最下位となっています。
この背景には、労働者が自身の体調不良や不測の事態に備えて有給休暇を取っておきたいという思いや人手不足、職場の協力が得られないことがあるようです。
一方で適切な休暇が得られれば、従業員の気分が前向きになったりモチベーションを上げたりすることができることもわかります。また若い従業員ほど、休暇の量次第では仕事を変えても良いと感じています。
厚生労働省の調査でも労働者ごとの有給休暇の取得率は52.4%となっています。また、事業所の規模が小さくなるほど取得率も下がっていく傾向が見られます。
有給休暇取得率が52.4%というのは、世界で比較すれば決して高い数値ではありません。
一方で有給休暇を取得しやすい職場を作ることは、有給休暇の取得の義務化という社会的な要請に応えるだけでなく、業務の効率化や採用活動にも良い影響をもたらす可能性があるでしょう。
計画的付与制度で取得率を向上させよう
とはいえ、どうすれば有給休暇の取得率を向上できるでしょうか?
ここからは、有給休暇の取得率を向上させるための制度である「計画的付与制度」をご紹介します。
計画的付与制度とは、あらかじめ労使間で有給休暇を取得する日を決めておき、その日に有給休暇を取得させる制度です。これを利用して飛び石連休などを事業所全体の休業日とすれば、従業員全体の有給休暇の取得率を向上させることができます。
ただし、制度の適用にあたっては、以下に挙げるいくつかの制限事項もあります。
これらに注意して導入を進めていきましょう。
指定できるのは5日分を除く日数
計画的付与制度であらかじめ取得日を指定できるのは、5日分を除く日数のみです。
たとえば、付与日数が12日分だった場合、取得日を指定することができるのは7日分となります。
事前に労使協定を締結する必要がある
計画的付与制度を適用するためには、まず「労使協定を結べばこれを実施して良い」という旨の記述を就業規則などに追記する必要があります。その上で労使協定を結び、ようやく導入することができます。
労使協定の具体的な内容については、厚生労働省のQ&Aを参考にしてください。
参考:4. 年次有給休暇の計画的付与について【労働基準法第39条関係】
時季の変更ができない
計画的付与制度を利用して有給休暇の取得日を設定した場合、やむを得ない事情がある場合を除き、従業員も雇用主もこれを変更することができません。これは通常の有給休暇とのかなり重要な違いです。
罰則の可能性に要注意
取得の義務化に伴い、有給休暇の取得に関するトラブルに遭遇することが増えるかもしれません。どのような対応をしてしまうと、罰則の可能性があるのでしょうか?
そもそも有給休暇を与えない
この記事でもお伝えした通り、雇用形態を問わずほぼすべての労働者には有給休暇が付与されます。これを少なくとも法律に規定の日数以上与えないことは禁止されています。
退職前に有休を消化させない
退職予定の従業員の中には、退職前に残っているすべての有給休暇を利用したいと希望する方もいるでしょう。雇用主はこれを拒否することはできません。ただしこの記事でもご説明したとおり、従業員が買い取りを希望する場合は、それに応じることはできます。
ただし、雇用主からの提案で買い取りを条件に有給休暇の取得を妨げることはできませんのでご注意ください。
有給を取った従業員の査定を下げる
有給休暇は労働者の権利のため、有給休暇を取得したことを理由にその従業員の取り扱いを左右することは禁止されています。たとえば有給休暇を取得したことによって査定を下げるなど、有給休暇の取得をさせないようにする対応はしてはいけません。また、有給休暇の申請をした従業員に不当に多くの業務を課するようなことも、してはいけません。
また、有給休暇を取得した日を欠勤扱いとすることはできません。賞与の計算や皆勤手当の計算上も出勤した日として計算してください。
時季変更権を過剰に行使する
雇用主に認められた権利に「時季変更権」があることは、この記事でも述べてきた通りです。しかしこれを過剰に行使し、結果として有給休暇を取得させないような対応を取ることは禁止されています。
時季変更権はあくまで、それを行使しなければ事業の継続が困難になる場合に限られます。行使する際は、業務上どのような差し迫った理由があるのか、いつならば取得できるのかを説明するようにしましょう。
まとめ
この記事では、有給休暇制度の基礎から、最近の義務化に関するトピックなど一般的な内容を一通り解説してきました。事業所の有給休暇制度の改善、義務化への対応など、有給休暇に関するお悩みごとは、ぜひ一度労務に関する法律知識の豊富な弁護士にご相談ください。