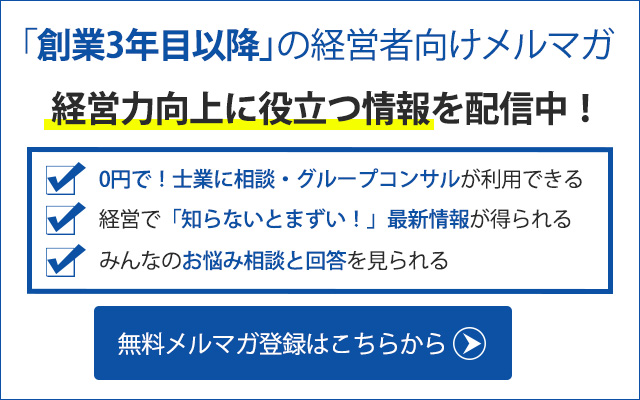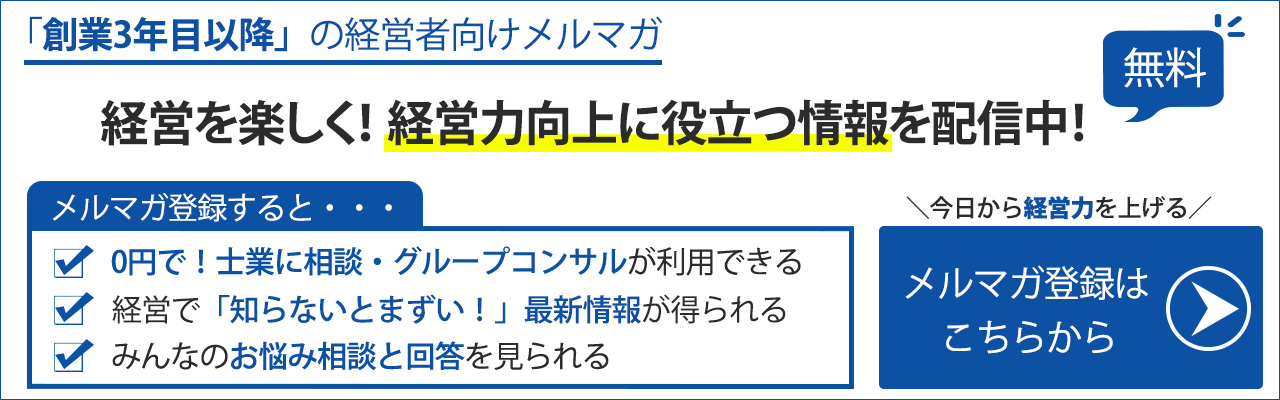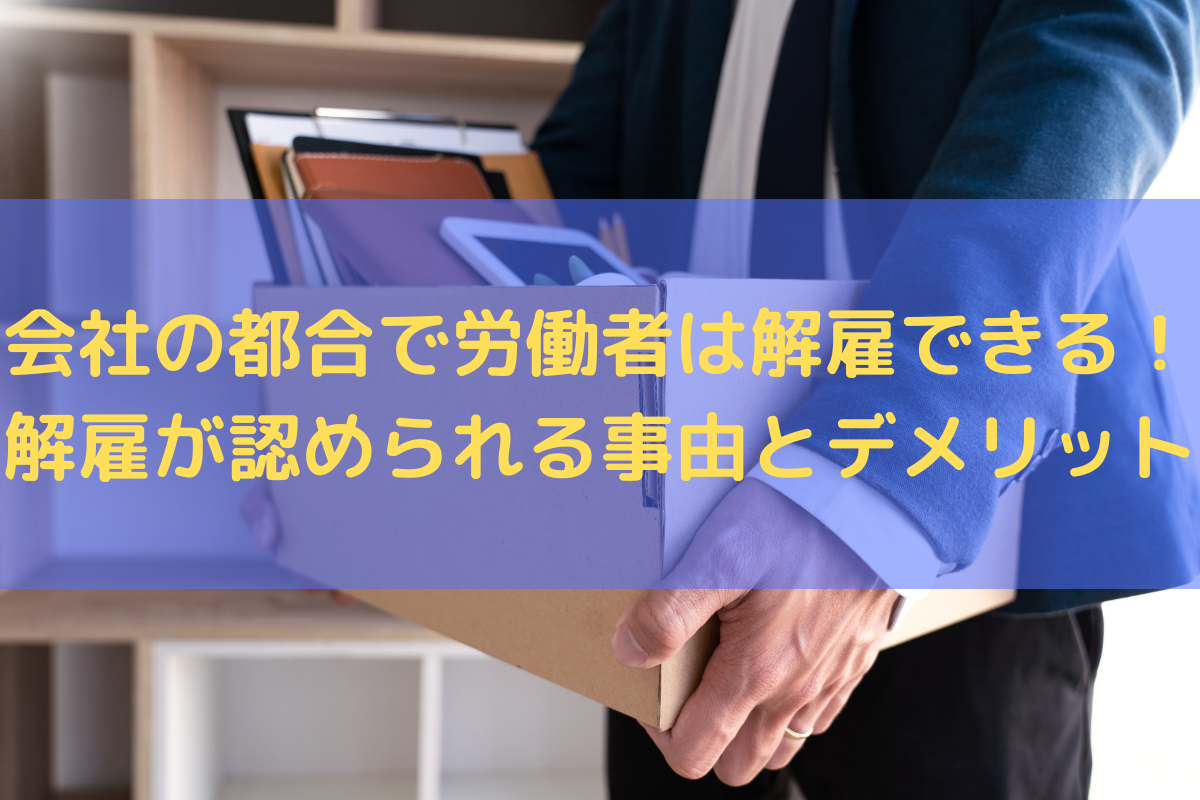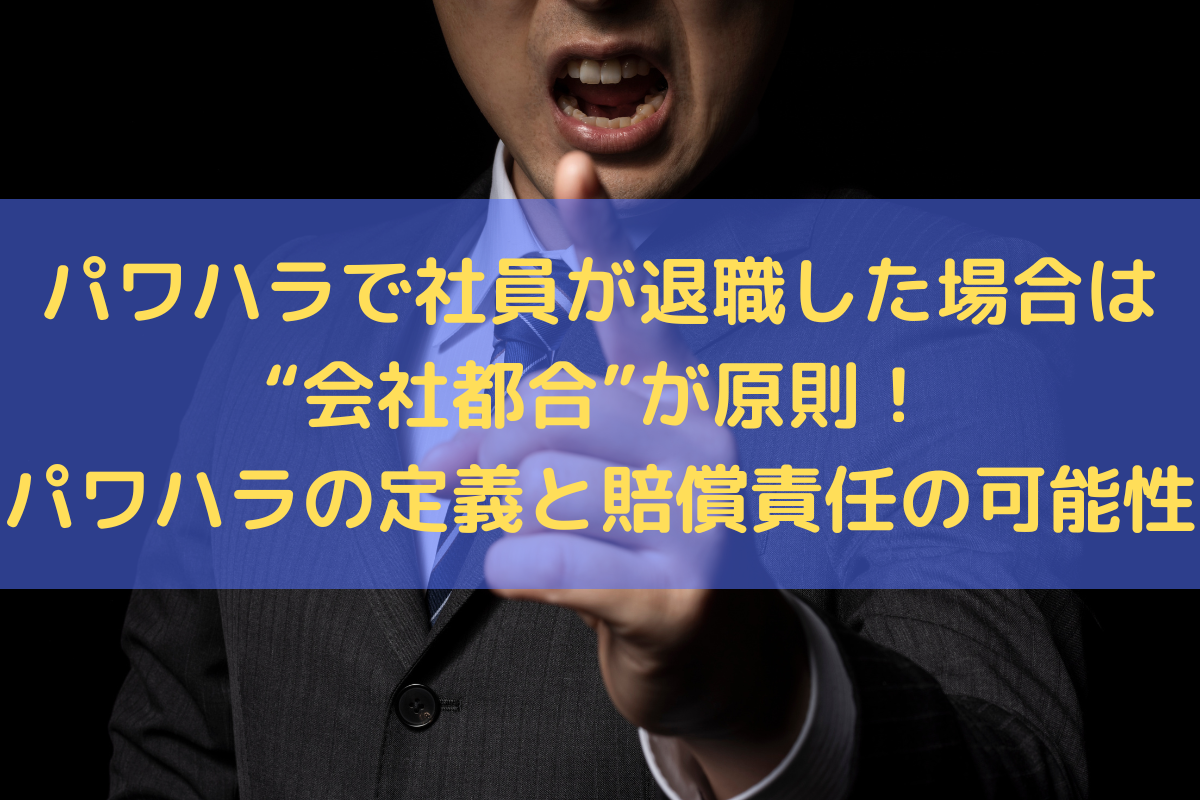【2023】雇止め法理とは?対象となる有期雇用契約・成立要件を弁護士がわかりやすく解説
「雇止め法理」とは、有期労働契約の雇止めに関する判例が蓄積し、ルール(判例法理)化されていたものです。これが、平成24年(2012年)8月10日に公布された改正労働契約法によって、法律へと格上げされました。
そこで今回は、有期労働契約者を対象にした雇止め法理について、過去の判例を交えながら弁護士が解説していきます。企業側においてどのような対応をすべきなのか参考にしてください。
雇止め法理とは?
雇止め法理とは、いわゆる「雇止め」を法的に制限することのことを言います。
そもそも雇止めとは、有期労働契約を締結している労働者に対して、契約期間満了をもって更新をしない旨を通知し、実際に契約を終了させることです。
契約期間に定めがあるとは言いつつも、人々が生きていくためには労働の対価として金銭を受け取らなければいけません。そのため当然、労働できる場所を不安定にするわけにはいかないため、雇止めが問題視されていました。
とくに、契約期間の更新が当たり前だと思っていた労働者からすれば、突然契約終了を言い渡されてしまうことで、生活にも影響をあたえる結果になるでしょう。こういった観点から、雇止めに関するルールを定めたものが雇止め法理の根本です。
そして、過去の最高裁判例等(判例法理)を原理として、できたものが雇止め法理です。簡単にいえば「雇止めに関する最高裁判例(判例法理)をもとに蓄積されたものを雇止め法理と呼ぶ」と思っておけば良いでしょう。
そして、この雇止め法理が法定化され、労働基準法に明記されるようになりました。まずは、雇止め法理の法定化やその内容について詳しくお伝えします。
判例法理の法定化(労働契約法19条)
雇止め法理が法定化される前までは、法律としての効力がなかったため、雇止めに関する意義を申し立てようとすれば裁判の判決を受けるしかありませんでした。しかし、雇止め法理の法定化に伴い、企業側は安易に雇止めをできなくなったので注意しなければいけません。
雇止め法理に関する法律は「労働契約法第19条」によって、下記のように定められています。
(有期労働契約の更新等)
第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128_20200401_430AC0000000071&keyword=労働契約法
つまり、下記に該当する有期雇用契約労働者に対して合理的な理由なく、雇止めをしてしまうと労働契約法に違反します。
過去に何度か更新がされていて、無期労働契約と同視できる場合
労働者が「当然に契約が更新されるだろう」と思える合理的な理由がある場合
詳しくは、次項で詳しくお伝えしているので参考にしてください。なお、労働契約法には罰則規定がありません。よって、雇止め法理に違反したからといって、罰則を受けることはないでしょう。
しかし、雇止めが無効であると判断されれば、当然に損害賠償請求の対象になり得ます。会社の信用も著しく低下させてしまう恐れがあるため、雇止め法理に関する知識をしっかりつけたうえで正しく対処されたほうが良いでしょう。
有期労働者を保護する法理
雇止め法理とは、有期労働契約者を守るための法理であって法定化されました。雇止め法理がなければ、企業は契約期間の満了を持って合理的な理由もなく、雇用契約を終了させられるようになります。
その結果、使用者が法に抵触することなく解雇が容易になるような仕組みになってしまいます。そうなると、有期労働契約者の生活や心身が不安定な状態になってしまうため、いくつもの最高裁判例をもとに雇止め法理が完成していきました。
どちらかといえば、雇止め法理は【使用者<労働者】の法理であると思っておいてください。
雇い止めが認められる合理的な理由
雇止め法理が法定化されたからといって、有期労働契約者への雇止めがすべて認められないわけではありません。雇止めについて客観的に合理的な理由があるのであれば、雇止めが認められます。
雇止めが認められる可能性のある「合理的な理由」の例は次のとおりです。
ただし、実際にはこれに該当するかどうか、微妙なラインであることも少なくないでしょう。そのため、実際に雇止めをしようとする際には自社のみで判断するのではなく、あらかじめ労使問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
臨時性のある職務で有期労働契約を締結したこと
そもそもその有期労働契約が過去に反復更新されたことがなく、労働者においてその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由もない場合には、契約期間の満了によって労働契約が終了することとしても問題ないでしょう。
この合理的な理由の有無については、最初の有期労働契約の締結時から雇止めされた有期労働契約の満了時までの間におけるあらゆる事情が総合的に勘案されます。
ただし、労働者が雇用継続への合理的な期待を抱いていたにもかかわらず、契約期間の満了前に使用者が更新年数や更新回数の上限などを一方的に宣言したとしても、そのことのみで合理的な理由の存在が否定されることにはならないと解されています。
通常の解雇同様の合理的な理由があること
有期労働契約であっても、次に挙げるものなど正社員の解雇が認められるほどの合理的な理由があるのであれば、雇止めが認められます。
ただし、雇止めの場合には、正社員の解雇よりはやや緩やかに判断されている場合が多いようです。とはいえ、その就労実態(これまでの更新回数など)が正社員と近似している場合には、正社員の解雇と同程度に厳しく判断される可能性があります。
素行不良
著しい素行不良や従業員による不正行為などがある場合には、雇止めに合理性があると認められる可能性があります。ただし、正社員ほど厳しい解雇回避義務までは求められないことが一般的です。
とはいえ、一度や二度遅刻をした程度では、これを理由に雇止めをすることは困難でしょう。明確な線引きがあるわけではなく、判例と照らし合わせて判断するほかありませんので、判断に迷う場合には弁護士へご相談ください。
著しい能力不足
従業員に著しい能力不足がある場合には、雇止めに合理性があると認められる可能性があります。
ただし、適切な指導や研修をしないままに能力不足を理由に雇止めをした場合などには、違法であると判断される可能性が高いでしょう。雇止めが合理的であるとされるためには、指導をしても改善の余地がないことなどが必要です。
著しい経営不振
著しい経営不振がある場合には、解雇や雇止めが認められる可能性があります。ただし、著しい経営不振は、従業員側に非があるものではありません。
そのため、人員削減の必要性があることに加え、解雇などを回避する努力をしたことなどの状況から、有効性がより厳格に判断されます。
対象となる有期労働契約は?
雇止め法理がすべての有期労働契約者に適用されてしまえば、有期労働契約そのものの意味がありません。
よって、雇止め法理ではある程度範囲を絞って、対象の有期労働契約者を定めています。
- 無期労働契約と同視できると判断できるとき
- 労働者が更新されるものと期待する合理的な理由があること
雇止め法理の適用を受ける上記2つの条件について、判例も交えながら詳しくお伝えします。
①無期労働契約と同視できると判断できるとき
客観的に見て、無期労働契約と同視できると判断されたときは、雇止め法理の適用を受けることになるでしょう。
反復継続的に更新がされていた
雇用の通算期間
当該雇用の臨時性(正社員と同様の業務か否か等)
など
「無期労働契約と同視できると判断できるとき」と判断される雇用契約は大きく、いわゆる「実質無期契約タイプ」とも呼ばれています。
【実質無期契約タイプの特徴と判例】
実質的無期契約タイプは契約更新が形式的になっていることが多かったり、同様の地位にある労働者の雇止め事案がほとんどなかったりするのが特徴です。また、使用者が労働者に対して契約更新をするように思わせる言動が多いのも特徴であり、実質的に無期契約と同等と考えられるタイプをいいます。
このタイプの代表的な判例はいわゆる「東芝柳町工場事件」です。この事件では2か月間の雇用期間を反復継続的に更新し、1年〜3年超も契約されていた臨時工が突然更新されなかったことによって、解雇と同等と認められた事件です。
東芝柳町事件の争点は「契約更新をしない相当な理由があったか?臨時工は契約の更新をされないことが予測できたか?」という点でした。
判決では、2か月間の契約が反復継続的に更新されていたことなどから、景気変動等による労働力の過剰状態でなければ当然に更新されるものと認識されるとの判断が下されました。東芝柳町事件と同様の事案では、実質無期契約タイプに分類され正社員の解雇と同様と判断されたため雇止めは認められません。
参考:労働基準判例検索
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/00377.html
②労働者が更新されるものと期待する合理的な理由があること
客観的に見て、労働者が「その契約更新が当然されるもの」と、期待できる合理的な理由があるときは雇止め法理に違反することになるでしょう。労働者が勘違いをしてしまう(契約更新を期待する)合理的な理由は下記のようなケースです。
使用者から労働者に対して契約を更新する旨を感じさせる発言があった
他に契約期間満了をもって契約を終了させた事例がない(多くのケースで契約更新がなされている)
更新回数が多く、他の労働者と同等の業務をこなしている
など
労働契約法では「労働者が更新されるものと期待する合理的な理由があること」と定められていることから、労働者が一方的に勘違いをしていたとすれば認められるのか?と言えば、そうではありません。
実際には、契約開始から契約期間満了までの期間に、使用者側から「思わせぶり」があったか否かを客観的に判断します。よって、労働者側からの判断ではなく、あくまでも客観的に見て(過去の判例を踏まえながら)総合的に判断されます。
そのため、初回の契約更新であったとしても、使用者側から思わせぶりな言動等があって労働者に誤認させてしまったときは、雇止め法理の範囲内になり得るでしょう。過去には「労働者が更新されるものと期待する合理的な理由がある」に関する下記のような判例がありました。
【判例の概要】ジャパンレンタカー事件
この労働者は6か月に1回の更新で約22年間勤務していましたが、体調不良を原因に休職。その後、復職を目指しましたがシフトに入れてもらえず、レンタカー会社(勤務先)からも連絡がなくそのまま雇止めをされた事件です。
この事件の争点は、「労働者が更新されるものと期待する合理的な理由があったか?」です。6か月間の契約更新が複数回行われ、実際に22年間も勤めたなら合理的な理由があったと認められています。
参考:裁判例|ジャパンレンタカー事件(津地裁 平28.10.25判決)
https://www.1roumshi.com/wp-content/uploads/2017/03/b8683781f5fbaff5e286f40f7063098c.pdf
雇止め法理がもたらす効果
雇止め法理や雇止めを制限する労働契約法の規定がなければ、あらかじめ取り決めをした期間の満了とともに労働契約を終了させても、問題はないはずです。
では、雇止め法理は、どのような効果をもたらすのでしょうか?主な効果は、次のとおりです。
以前と同じ条件で有期労働契約の更新が行われる
雇止め法理やこれが明文化された労働契約法の規定によって雇止めが無効となった場合には、「使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみな」されることとなります。つまり、雇止めが無効と判断されれば、従前と同じ条件で有期労働契約の更新がなされるということです。
無期労働契約への更新がなされることもある
雇止めが無効となり同一条件で有期労働契約が更新されたことによって有期労働契約が通算して5年を超えることとなった場合には、労働者からの申込みにより、無期労働契約へと転換されることとなります。これを、「無期転換ルール」などといいます。
労務管理上の対策
雇止め法理を踏まえ、労務管理上はどのような対策を講じれば良いのでしょうか?企業が講じるべき主な対策は、次のとおりです。
雇用期間の管理を徹底する
有期労働契約で従業員を雇用する場合には、従業員ごとに期間の満了日を把握し、管理することが必要です。
そのうえで、期間満了日の1ヶ月以上前には、契約満了の通知を出すよう徹底しておきましょう。期限管理ができておらず、期限満了後も黙示で契約が更新されていることが常態化すれば、雇止めのハードルが高くなる可能性があるためです。
また、次回は更新しないのであれば、契約書にその旨を明記しておくと、次の期間満了時に雇止めが行いやすくなります(ただし、契約書にさえ記載しておけば必ず雇止めが適法となるわけではありません)。
業務内容の限定を検討する
有期労働契約で従業員を雇用する際は、業務内容をできる限り特定し、これを契約書に定めておくと良いでしょう。業務内容を限定することで、この業務がなくなった時点での雇止めが合理的であると判断されやすくなるためです。
ただし、業務内容を限定した場合には、従業員を他の業務に従事させようとした際に、従業員から契約内容に反するとして拒否されるリスクもあるでしょう。
契約更新回数の上限を定めておく
有期労働契約で従業員を雇用する際には、あらかじめ更新回数の上限を定め、これを契約書に記載しておくことも一つの手です。これにより、この回数を超えて更新されるとの期待を従業員に抱かせづらくなり、雇止めがしやすくなる可能性があるでしょう。
また、回数の上限を定め5年を超えて雇用しないようにすることで、無期転換ルールが適用されるリスクを避けることが可能となります。
雇止め法理の注意点
雇止め法理に関して、企業はどのような点に注意すれば良いのでしょうか?主な注意点は、次のとおりです。
安易な言動を行わない
企業側や人事担当者は、有期労働契約となっている従業員に対して、安易な言動をしないよう注意しなければなりません。
いくら契約書などで更新回数の上限や次回は契約更新をしないことなどを定めていても、会社側が日ごろからこれを超えて更新することなどを匂わせる言動をしている場合などには、雇止めが違法であると判断される可能性があるためです。
そのため、不用意に更新の期待を抱かせるような言動をすることは、慎むべきでしょう。
行政が示す基準をよく理解する
厚生労働省では、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が定められています。経営陣や人事担当者はこれをよく読み、理解しておく必要があるでしょう。
厚生労働省などが作成している「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」というリーフレットには、具体的な基準などが非常によくまとまっていて、参考となります。
不明点はあらかじめ弁護士へ相談する
雇止めや解雇を誤った認識で行ってしまうと、大きなトラブルとなる可能性があります。解雇や雇止めで職を失った従業員は、生活の糧を失うことにもなりかねないためです。
万が一トラブルに発展してしまえば、訴訟などに時間や労力がかかる可能性が生じるほか、外部からの企業の評価が低下してしまうおそれもあるでしょう。そのため、雇止めや解雇に関する判断は、特に慎重に行うことをおすすめします。
不明点がある場合には無理に遂行するのではなく、労使問題にくわしい弁護士にあらかじめ相談をするとよいでしょう。弁護士へ相談することで、行おうとしている雇止めの適法性を確認したうえで、法令で求められている手続きに沿って雇止めを行うことが可能となります。
また、万が一訴訟へと発展しても弁護士に対応を任せられるため安心です。さらに、雇用契約書の内容を検討するなど、予防策へのアドバイスを受けることもできるでしょう。
まとめ
「一度雇用契約を締結すると、解雇するのは難しい」という考え方は、すでに浸透しているかと思います。そしてこれは、無期で雇用している正社員のみならず、有期労働契約であっても例外ではありません。
有期期間契約であるからといって自由に契約を打ち切る事ができるわけではありませんので、誤解のないよう注意したうえで、対策を講じておきましょう。
雇止めなどに関する労務トラブルは、企業経営に大きく影響しかねない重要な問題です。
もちろん裁判になってからの対応も可能ではあるものの、たきざわ法律事務所では、トラブル前の「予防」が最重要だと考えております。
労務関連で少しでもトラブルがある企業様や不安のある企業様は、たきざわ法律事務所までお気軽にご相談ください。訴訟対応はもちろん、訴訟前の対応や訴訟を起こさないための体制づくりのサポートをいたします。