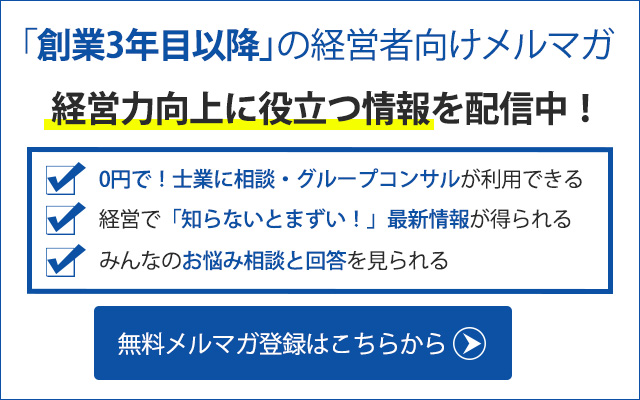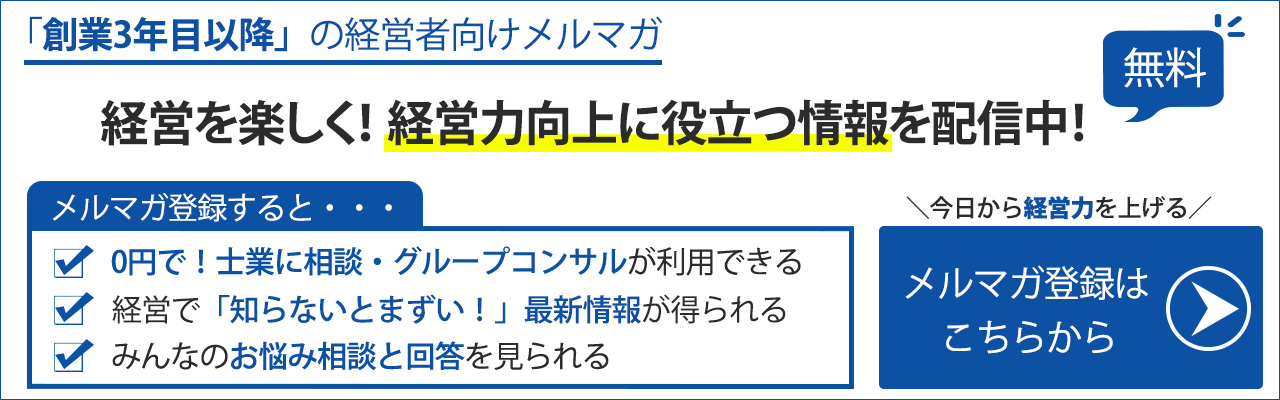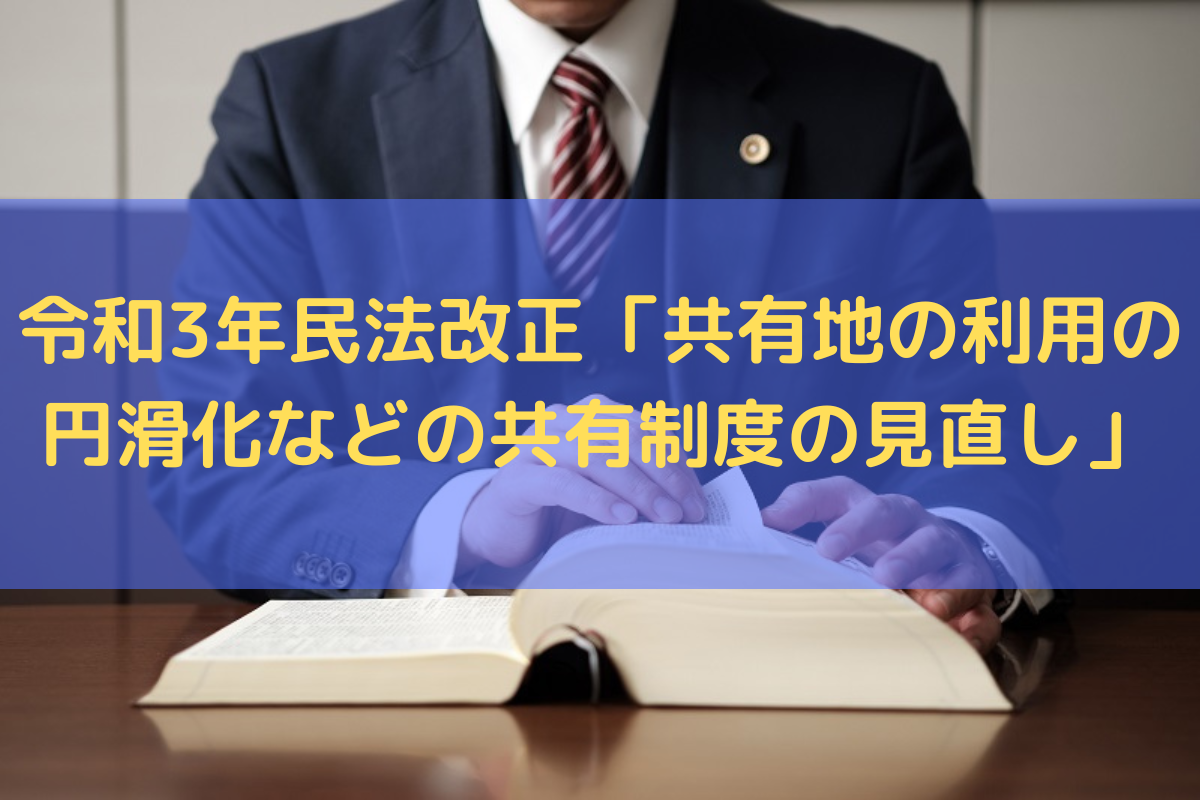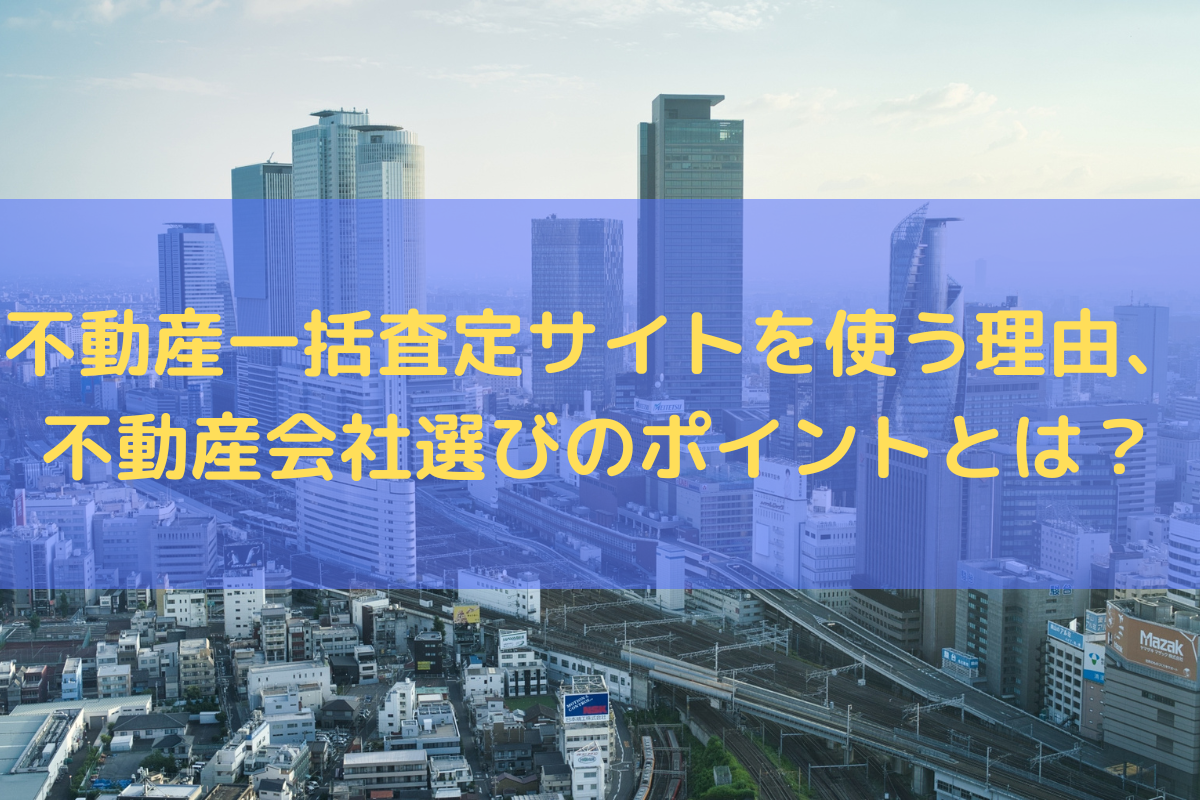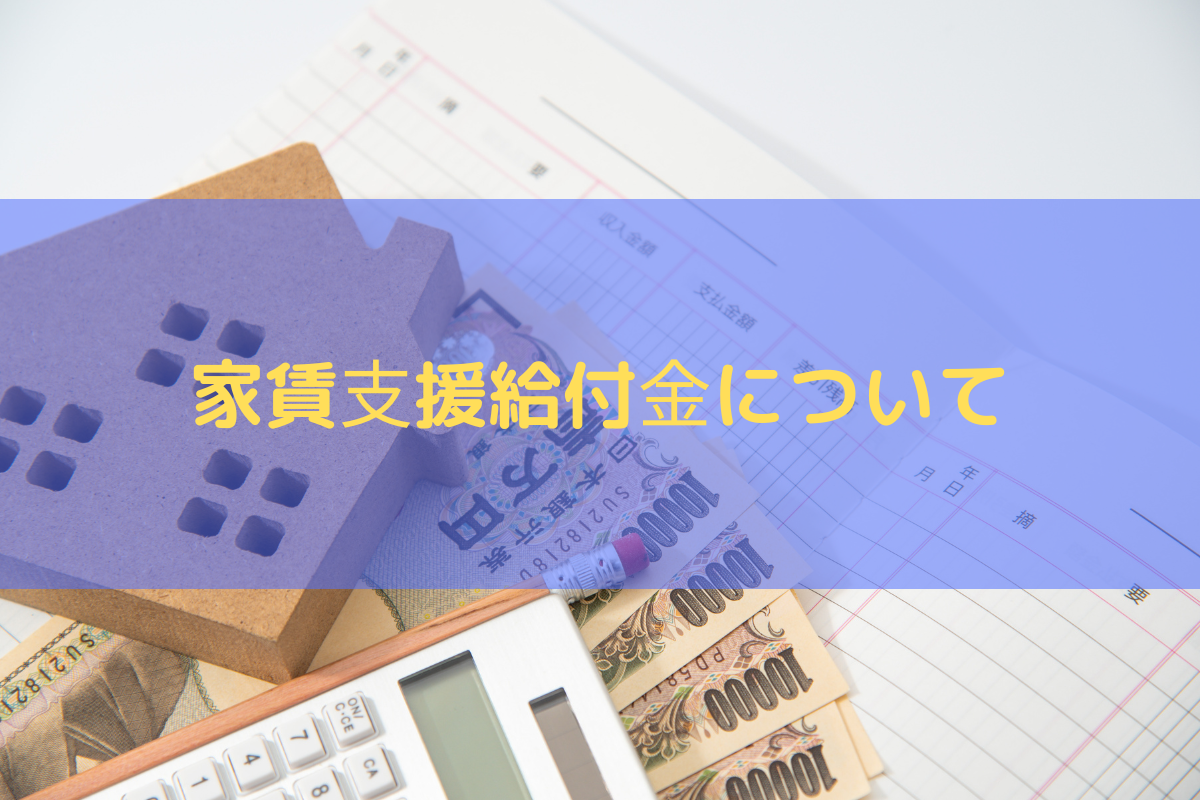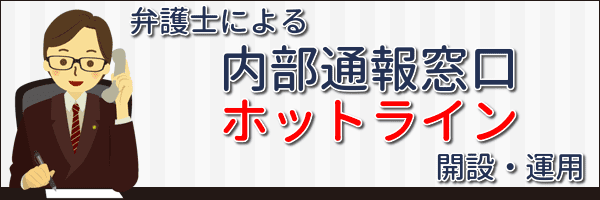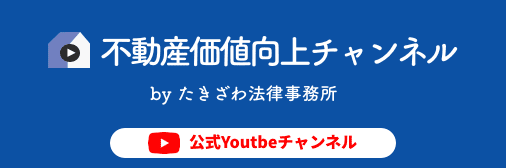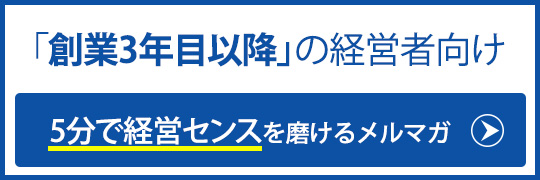所有者不明土地を買いたい場合の手続きとは?弁護士が解説
所有者が不明となっている土地を買いたい場合、買うための方法はあるのでしょうか?
従来は、買いたい土地の所有者が不明である場合、これを買うことは、ほぼ不可能でした。しかし、令和5年(2023年)4月1日に施行された改正法によって、所有者が所在不明である土地を買うためのハードルが少し下がっています。
改正によって創設された制度を活用すれば、これまで諦めていた所有者不明土地の購入が実現できるかもしれません。今回は、所有者不明土地を買う方法や所有者不明土地を買うリスクなどについて、改正で新たに誕生した制度を踏まえてくわしく解説します。
目次
所有者不明土地とは
所有者不明土地とは、土地の所有者が誰であるのかわからない土地や、所有者はわかるもののその所有者と連絡が取れなくなっている土地を指します。
これまでは、買いたいと希望する土地の所有者や共有者の一部が所在不明である場合、その土地を購入することは困難でした。なぜなら、そもそも買い取り交渉をしようにも誰と交渉すればよいのかわからないうえ、交渉相手と連絡を取る手立てもないためです。
しかし、所有者不明土地が増えれば利活用ができない土地が増えてしまいます。こうした事態を受け、所有者不明土地を増やさないための制度や、所有者不明土地を利活用しやすくするための制度が改正によって数多く誕生しました。
これらの改正は令和5年(2023年)4月1日より順次施行されています。
所有者不明土地が生まれる理由
土地の所有者の住所氏名は、その土地の登記簿に記録されています。そのため、本来であれば、その土地の登記簿謄本(全部事項証明書)を取得することで、土地所有者の住所氏名が分かるはずです。
では、なぜ所有者不明土地が生まれてしまうのでしょうか?指摘されている主な原因は、次の2点です。
住所変更登記の放置
1つ目の原因は、住所変更登記の放置です。
住所変更登記とは、不動産の所有者が引っ越して住民票上の住所が変わった際に法務局で手続きをして、登記簿謄本に記載されている住所を書き換えてもらう手続きです。
しかし、住所変更登記は義務ではなかったため、引越しをしても住所変更登記を行わないケースが少なくありませんでした。その結果、登記簿謄本を取っても引越し前の古い住所しか載っておらず、所有者と連絡が取れないケースが散見されます。
なお、改正により、引越し後2年以内の住所変更登記が義務化されました。また、本人の了解があるケースに限り、登記官が他の公的機関から取得した情報にもとづいて職権で住所変更登記をする仕組みが導入されることとなっています。これらの改正は、令和8年(2026年)4月までに施行される予定です。
相続登記の放置
もう1つの原因は、相続登記の放置です。相続登記とは、不動産の名義人が亡くなった後、不動産の名義を相続人などへと変える手続きです。
しかし、住所変更登記と同じく相続登記も義務ではなかったため、相続登記をしないままで放置されるケースが少なくありませんでした。その結果、登記簿謄本を取ってもそこに記載のある名義人がすでに亡くなっており、現在の権利者が誰であるのか分からないケースが散見されます。
また、登記簿謄本上の名義人が亡くなってからかなりの年数が経過することで、数代にわたり相続が繰り返され、もはや現在の権利者を探し出すことが困難となっている場合もあります。中には、権利者が誰も、自分にその土地の権利があることさえ知らない場合もあるでしょう。
なお、改正により、不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記をすることが義務化されました。この改正は、令和6年(2024年)4月1日に施行されます。
所有者不明土地を買いたい場合の手続き
所有者不明土地を買いたい場合には、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか?基本的な流れは次のとおりです。
全部事項証明書で権利関係を調査する
はじめに、土地の全部事項証明書を取得して、登記簿上の所有者や共有者を確認します。全部事項証明書は、全国どこの法務局からでも、誰でも取ることが可能です。
その所有者や共有者の住所地に手紙を送るなどして、連絡をとることを試みましょう。
相続関係をたどって現在の所有者を調査する
登記簿上の所有者がすでに亡くなっている場合には、戸籍謄本をたどるなどして現在の所有者である相続人を探す必要があります。
しかし、戸籍謄本は重大な個人情報であるため、単に土地を買いたいという理由だけでは取得することができません。そのため、現実的には、行方不明者の親族またはその土地の共有者など、利害関係人の協力が不可欠でしょう。
利害関係者の範囲が不明であるなどお困りの場合には、弁護士へご相談ください。
現在の権利者と連絡を取る
現在の権利者(共有者)が一部でも判明したら、権利者と連絡を取りましょう。共有者や親族などが売却に前向きなのであれば、これらの者の協力を得ることで、この先で解説をする具体的な方法に進むことが可能となります。
所有者不明土地を買う方法:現在の権利者が誰もいない場合
買いたい土地の権利者のうち、所在が判明している人が誰一人いない場合には、どのような方法をとることができるのでしょうか?たとえば、買いたい土地が、ある人物(仮に、A氏とします)の単独所有であり、そのA氏の所在が不明な場合などです。
考えられる方法としては、次のものが挙げられます。
不在者財産管理人制度を活用する
土地・建物に特化した財産管理制度を活用する
このうち「不在者財産管理人制度」は従来から存在するものの、特定の購入を目指すという観点では、使い勝手はよくありません。今回の改正で新たに「土地・建物に特化した財産管理制度」が誕生したことで、所在者不明土地の流通が期待されています。
不在者財産管理人制度を活用する
この場合に利用できる可能性がある制度の1つ目は、「不在者財産管理人制度」です。
不在者財産管理人制度とは、従来の住所や居所を去り容易に戻る見込みのない者(不在者)の財産を管理する人を、家庭裁判所に選任してもらう制度です。不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得ることで、不在者名義の財産を売却することもできます。
ただし、不在者財産管理人は不在者の財産を包括的に管理する立場であり、土地など一部の財産のみを管理するわけではない点に注意が必要です。また、複数の所有者が所在不明である場合には不在となっている「人」単位で制度を利用する必要があるため、煩雑となります。
さらに、所有者をまったく特定できない土地については、この制度を利用することはできません。
土地・建物に特化した財産管理制度を活用する
土地・建物に特化した財産管理制度とは、特定の土地や建物のみに特化して管理を行う所有者不明土地管理制度です。管理人は裁判所の許可を得ることで、管理する土地などを売却することも可能です。
土地の売買を前提とする場合には、主に次の点で、不在者財産管理人制度よりも使い勝手がよいといえるでしょう。
この制度の管理者は所在不明者の財産を包括的に管理するわけではなく、特定の土地や建物のみを管理する点
土地が共有であり複数の共有者が所在不明である場合であっても、まとめて1人の管理者が管理することができる点
土地所有者がまったく不明である場合にも、制度を利用することができる点
制度利用の要件
土地・建物に特化した財産管理制度を利用するための主な要件は、次のとおりです。
調査を尽くしても「所有者」または「所有者の所在」を知ることができないこと
管理状況等に照らし、管理人による管理の必要性があること
マンションの1室など、区分所有建物ではないこと
なお、所有者が一般個人である場合に尽くすべき調査としては、登記簿や住民票上の住所、戸籍などが挙げられます。調査でお困りの際には、弁護士へご相談ください。
制度を利用して土地を売るまでの流れ
土地・建物に特化した財産管理制度を利用して所有者不明土地を売却するまでの主な流れは次のとおりです。
調査:所有者が所在不明であると言えるだけの調査を行います
申立て・証拠提出:利害関係者が、不動産所在地の地方裁判所に申し立てます
異議届出期間の公告:1ヶ月以上の異議届出期間等を定めて公告されます
管理命令の発令と管理人の選任:管理人には、弁護士や司法書士、土地家屋調査士など事案に応じて管理人としてふさわしい者が選任されます
その後、選任された管理人が裁判所の許可を得ることで、対象となっている所有者不明土地の売却が可能となります。また、土地上に建物が建っている場合には、管理人が裁判所の許可を得て建物を取り壊すことも可能です。
ただし、売却にあたっては、借地関係などの利用状況や売買の相手方を慎重に調査することが管理人に求められています。
施行日
土地・建物に特化した財産管理制度は、令和5年(2023年)4月1日に施行されました。
所有者不明土地を買う方法:現在の権利者の一部が不明な場合
買いたい土地が共有となっており、共有者の一部が所在不明である場合には、次の方法が検討できるでしょう。今回の改正で新たに誕生した制度です。
所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡制度を利用する
所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡制度とは、所在不明である共有者の持分を売却する権利を、他の共有者である申立人に付与する制度です。
原則として、たとえば土地がA、B、Cの共有でありAの所在が不明である場合、たとえAの共有持分割合が小さかったとしても、BとCだけの判断で土地全体を売却することはできません。
もちろん、BとCさえ同意すればBとCの持分のみを買い取ることはできるものの、所在不明であるAの持分が入ったままである以上、買い取ったところで使い道が非常に限定されてしまうでしょう。
そこで新たに誕生したのが、この制度です。所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡制度を利用することで、BとCのみの判断により、Aの持分を含めて土地全体を売却することが可能となります。
制度利用の要件
所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡制度を利用するための主な要件は、次のとおりです。
登記簿や住民票などで必要な調査をして、裁判所において共有者が所在不明であると認められること
もともとの名義人が亡くなったことで自動的に共有となっている遺産共有のケースでは、相続開始から10年を経過していること
所在等不明共有者以外の共有者全員が持分の全部を譲渡すること
制度を利用して土地を売るまでの流れ
所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡制度を利用して土地を売るまでの基本的な流れは次のとおりです。土地がA、B、Cの共有であり、Aの所在が不明である前提で解説します。
調査:登記簿や住民票などで、Aが所在不明であると認められるために必要な調査をします
申立て・証拠提出:共有者(仮に、B)が、不動産所在地の地方裁判所に申し立てます
異議届出期間の公告:3ヶ月以上の異議届出期間等を定めて公告されます
供託:土地の時価相当額のうち、Aの持分相当額を供託します。時価の算定にあたっては、第三者に売却する際に見込まれる売却額などが考慮されます
譲渡権限の付与:Bに、Aの持分の譲渡権限が付与する裁判がなされます
売却:BとCで、土地全体を第三者に売却します
このように、この制度を利用することで、土地の共有者の一部が所在不明であっても売買をすることが可能となります。
施行日
所在等不明共有者の不動産の持分の譲渡制度は、令和5年(2023年)4月1日に施行されました。
所有者不明土地の購入にあたり知っておくべきリスク
所有者不明土地を買いたい場合は、購入のリスクを知っておく必要があります。所有者不明土地を買うことで生じる可能性がある主なリスクを3つ解説します。
交渉が難航するおそれがある
1つ目は、交渉が難航するおそれがあることです。たとえば、故人名義のままで放置された所有者不明土地の現在の権利者を探して購入の交渉をしたとしても、スムーズに交渉がまとまるとは限りません。
自分が権利者であることさえ知らないケースもある一方で、先祖代々の土地を守りたいなど何らかの事情によってあえて故人名義のままとしている可能性もあるためです。
また、名義変更や売却ができない何らかの事情(共同相続人の1人に知的障がいがありそのままでは遺産分けの話し合いができないものの、後見人を付けることは避けたいなど)がある場合もあるでしょう。
土地を買いたい側からすると放置しているくらいなので、購入を打診すれば応じてくれるだろうと考えるかもしれません。しかし、実際にはそのような単純なケースばかりではないことを理解しておく必要があります。
一部不明であった所有者が見つかった際にトラブルに巻き込まれる可能性がある
2つ目は、所在不明であった一部の共有者が見つかった際に、トラブルに巻き込まれる可能性があることです。
先ほど紹介した新しい制度ができたことで、たとえ複数の共有者のうち一部が所在不明であったとしても、他の共有者全員による協力のもと裁判手続きを経ることで、土地を売買することが可能となりました。裁判手続きの中では所在不明者を探す公告などを行うものの、たとえば指名手配犯などのように徹底的に探すわけではありません。
そのため、土地の売買が成立してから所在不明であった共有者が見つかることも考えられます。
この場合において「元・所在不明者」は供託された売買代金を受け取れるとはいえ、自分の知らない間に土地が売られたことに不快感を示すかもしれません。法律上は問題がなかったとしても、購入者に対し再三にわたる抗議がされる事態となれば、精神的なストレスとなり得ます。
整備費用が高額となるおそれがある
3つ目は、土地の整備費用が高額となるおそれがあることです。
所有者不明土地は草木が生い茂っていることが少なくありません。また、古い建物が倒壊寸前の状態で残っていたり、残置物があったりするケースもあります。
このような土地を使える状態にまで整備することに、多大な費用が生じる可能性があります。
まとめ
買いたい土地が所有者不明土地である場合であっても、新たな制度ができたことにより、購入の道が開かれることとなりました。これまでは購入を諦めざるをえなかった土地でも、今後は所在不明者の親族や他の共有者の協力を得ることで購入できる可能性が生じます。
ただし、所有者不明土地の購入にはリスクがあり、手続きなどの負担も必要です。そのため、所有者不明土地を購入した場合は、あらかじめ弁護士へ相談し、慎重に進めるようにしてください。
たきざわ法律事務所は不動産法務に力を入れており、なかでも所有者不明土地に関して多くの解決実績があります。所有者不明土地を買いたい場合や売りたい場合、所有者不明土地に関するトラブルでお困りの際などには、たきざわ法律事務所までご相談ください。