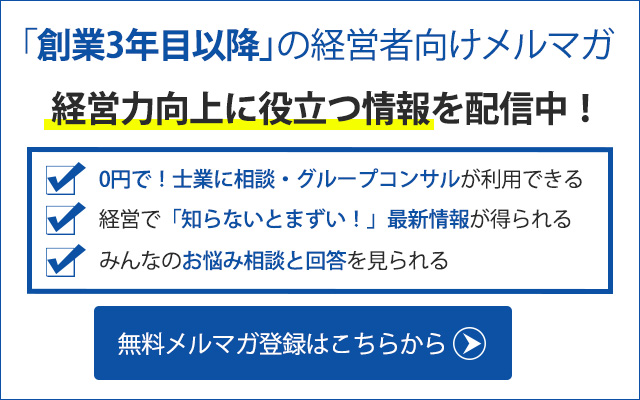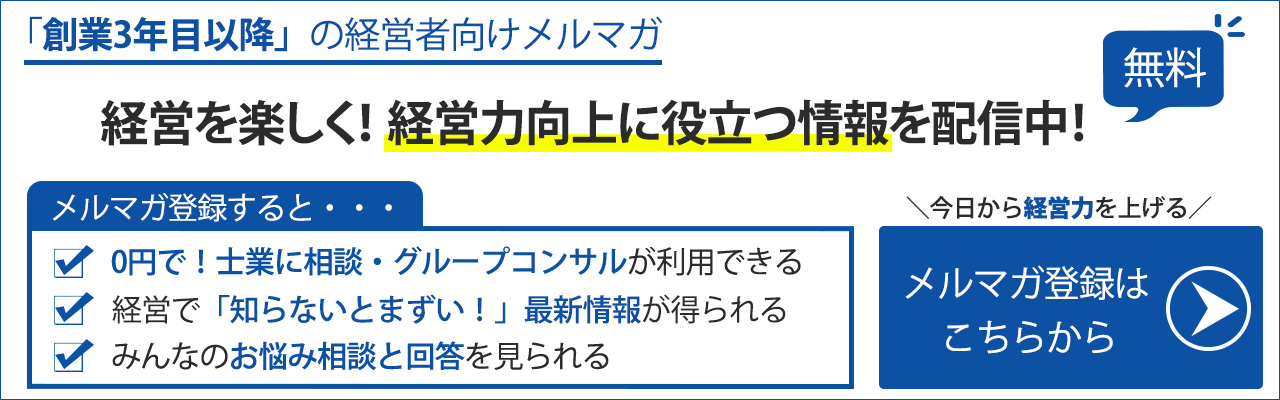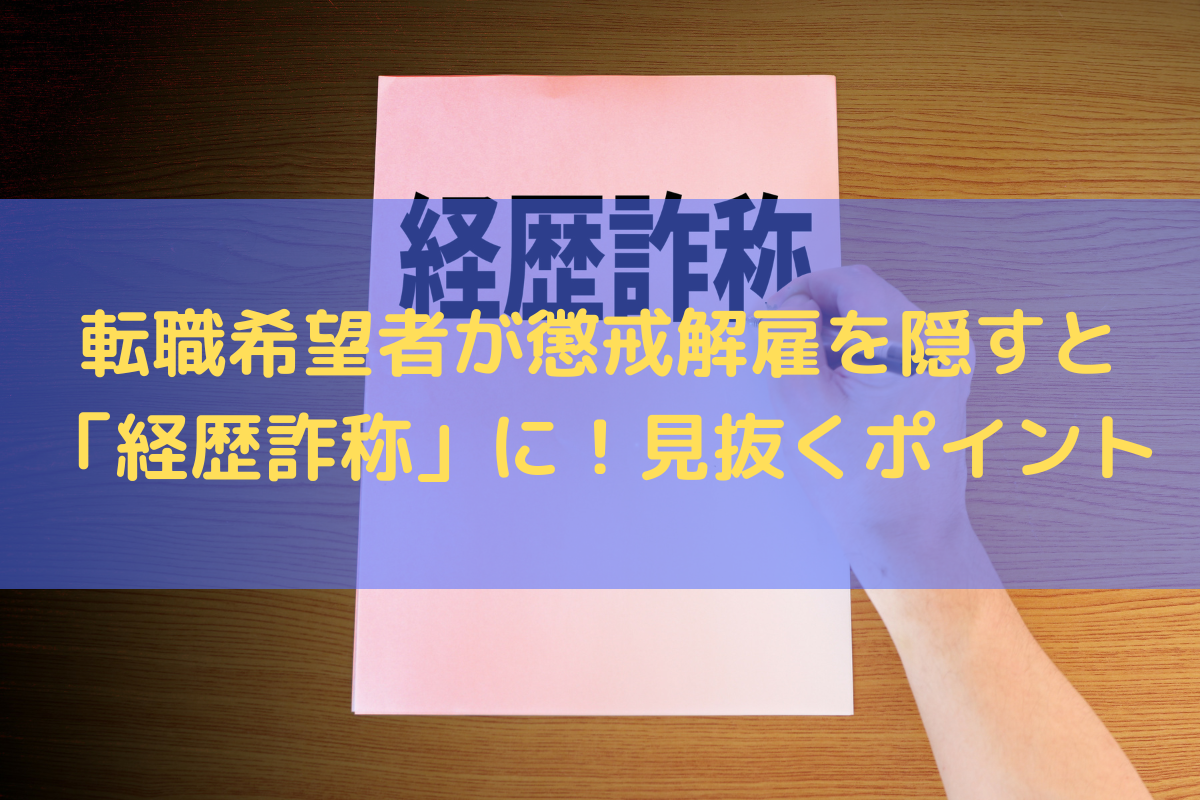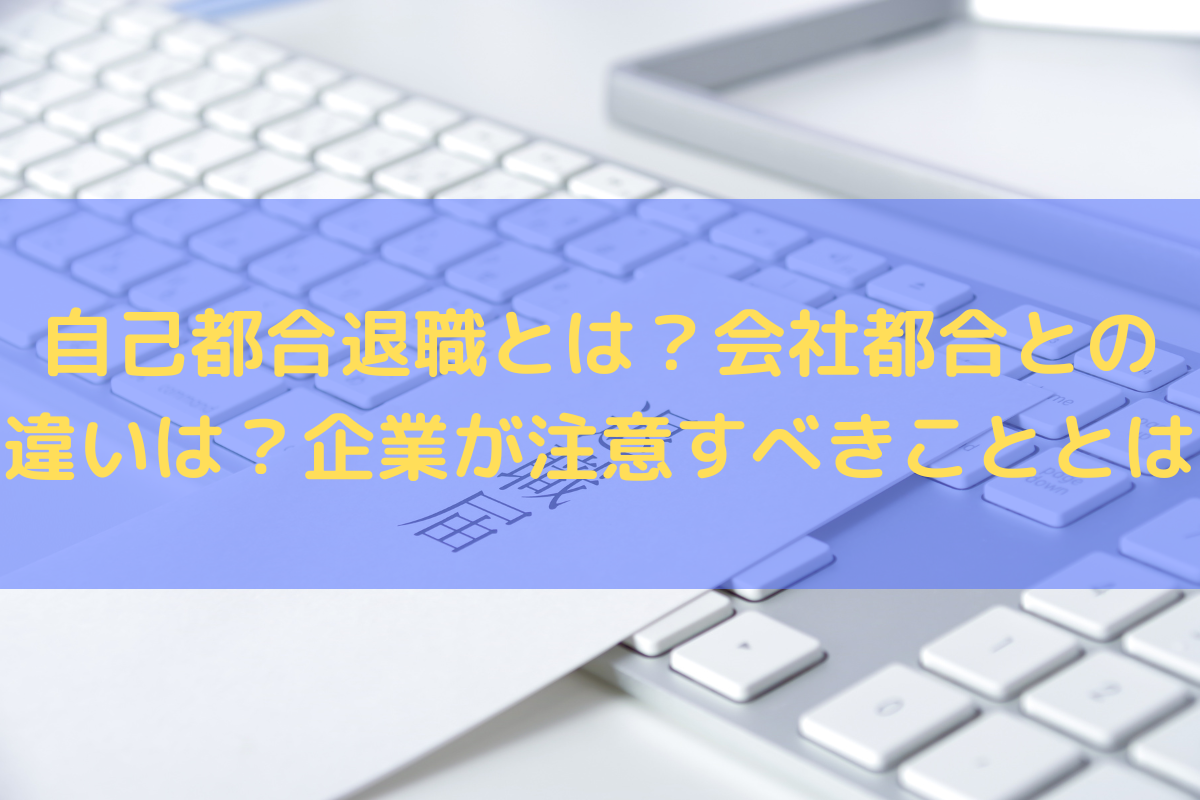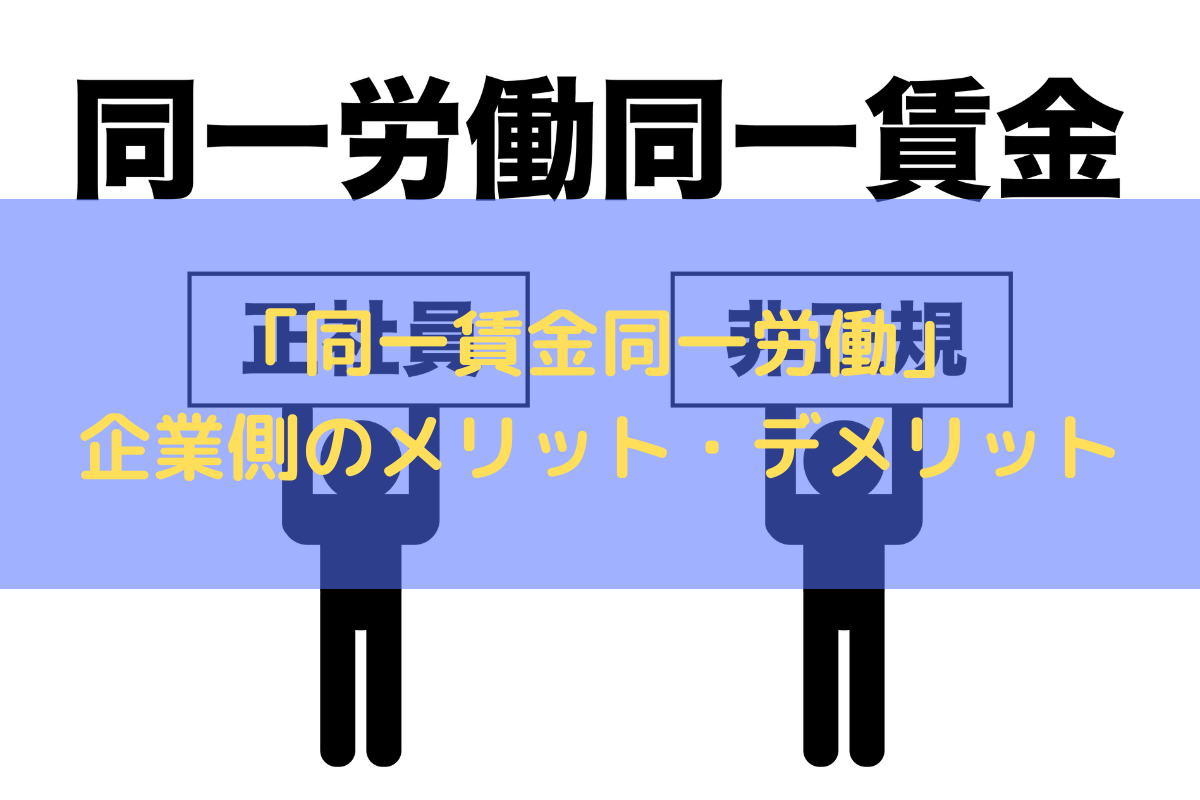正社員を「解雇」するには?解雇の種類と辞めさせる際の要件・手順
日本では、正社員を解雇することは難しいといわれます。しかしながら、会社側から正社員の労働者を辞めさせることができないわけではありません。
労働者側に責任があることを客観的に証明できれば、合法的に正社員の労働者であっても辞めさせることは可能です。今回は、正社員を辞めさせるにあたって押さえておくべき法律や解雇の流れについて解説します。
目次
正社員を辞めさせたい場合はどうしたら良い?
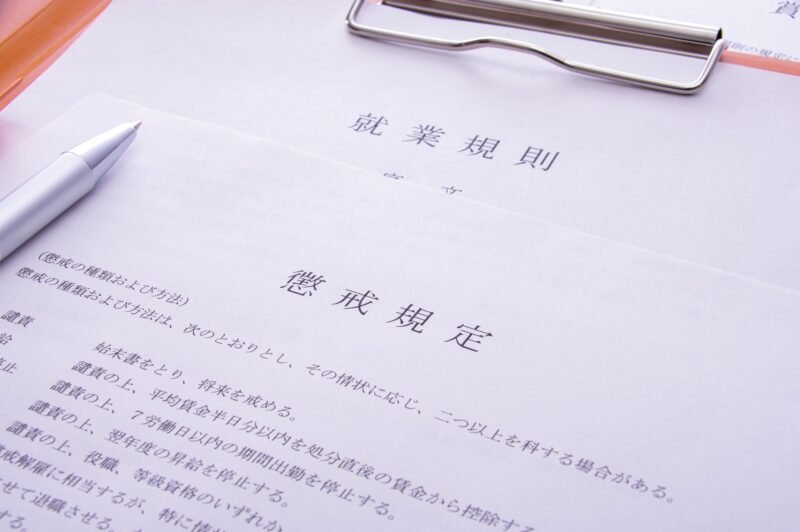
会社が労働者を突然解雇してしまうと、会社からの給与を生活の糧としている労働者の生活に多大な影響を及ぼします。この影響を緩和するため、労働基準法をはじめとした法律において、労働者を解雇する際の制限や手続きが定められています。
では、正社員を解雇したい場合、使用者はどのように対応したら良いのでしょうか?
解雇に関する法律を守る
解雇に関する法律には、たとえば次のようなものがあります。
労働基準法
労働組合法
男女雇用機会均等法
育児・介護休業法
これらの法律によって、一定の場合には法律で解雇が禁止されています。まずは、解雇をすることができない解雇禁止期間に該当しないか、解雇することができない事由ではないか確認しましょう。
各法律における主な項目は次のとおりです。
業務上災害のため療養中の期間とその後の30日間の解雇
産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇
労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇
労働者の性別を理由とする解雇
女性労働者が結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇
労働者が育児・介護休業などを申し出たこと、又は育児・介護休業などをしたことを理由とする解雇
解雇事由を明示する
突然の解雇を防止するため、あらかじめ解雇事由を明示することが求められています。就業規則や労働契約書(労働条件通知書)に、どのようなときに解雇されることがあるか解雇事由をあらかじめ示し、そして労働者の行動がその要件に合致することが必要です。
この要件は、法律改正により平成16年1月から新たに設けられました。それ以前に定められた就業規則等には具体的な解雇事由が記載されていない場合もありますので、この機会に見直しをしておきましょう。
解雇権の濫用による解雇は無効となる
先述のような労働基準法等で禁止されている条項に該当しない場合も、また就業規則や労働契約書によって解雇事由を明示していたとしても、解雇を自由に行えるというわけではありません。
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法第16条)と定められています。解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要なのです。
たとえば、「体調が悪く連絡できないまま無断欠勤をした」といったやむを得ない理由がある場合や、単に「商品を壊した」「服装がだらしない」といった理由だけで解雇することはできません。
解雇予告を行う
合理的な理由があって解雇を行うとしても、少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。
この解雇予告を行わない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として、支払う必要があります。
たとえば、解雇日の20日前に予告した場合は、10日×平均賃金を支払う必要があります(労働基準法第20条)。
解雇予告は、口頭でも有効です。しかし、口約束ではトラブルの原因となりますので、解雇する日と具体的理由を明記した「解雇通知書」を作成することが望ましいでしょう。
また、退職する労働者から解雇の理由について証明書を求められた場合は、会社はすぐに解雇理由を記載した書面を作成して本人に渡さなければなりません(労働基準法第22条)。
退職勧奨で会社の考えを伝える
退職勧奨とは、使用者が労働者に対し退職をすすめることをいいます。退職勧奨は解雇と混同されやすいのですが、労働者の意思とは関係なく使用者が一方的に契約の解除を行うのではなく、労働者の方に対して退職を促すための行為であり、実際に退職するか否かは労働者の自由意思によります。
このことから、退職勧奨では労働者の自由な意思決定を妨げないように注意しなければなりません。なお、労働者が退職勧奨に応じて退職した場合には、「自己都合」による退職とはならず「会社都合」の退職の扱いとなります。
解雇の種類
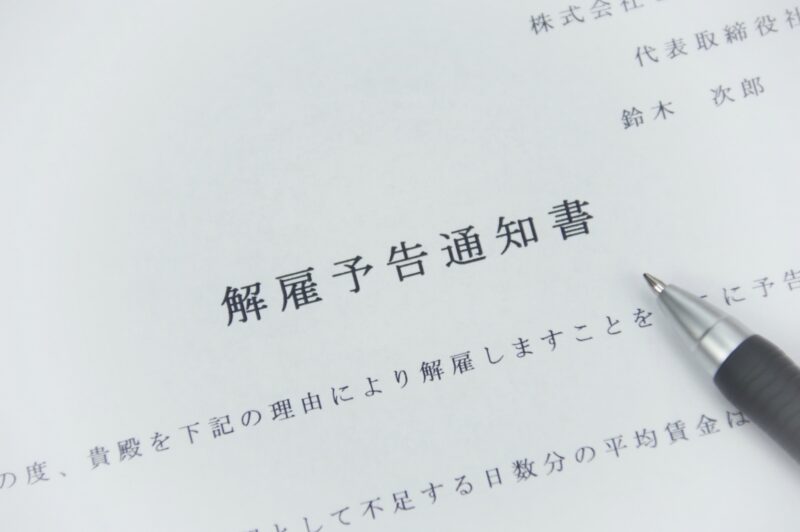
解雇には、次の3種類があります。そして、それぞれの解雇の種類に応じて、解雇の手続きも異なります。
普通解雇
整理解雇
懲戒解雇
まずは、それぞれの解雇の違いを押さえましょう。
普通解雇
普通解雇とは、労働者自身が仕事を続けられない事由に該当したことによる解雇のことです。整理解雇、懲戒解雇以外の解雇のことであり、一般的に解雇というときには、この普通解雇を指しています。
普通解雇を行うことができるのは、労働契約の継続が困難な事情があるときに限られており、その場合でも30日前の解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払わなければなりません。
整理解雇
整理解雇とは、会社の経営が悪化し、人員整理を行う必要性が生じたために行う解雇を指します。整理解雇でもやはり、30日前の解雇予告を行うか、解雇予告手当を支払わなければなりません。
普通解雇や懲戒解雇は、対象となる一人の労働者との労働契約を解除するために行う解雇です。一方、整理解雇はいわゆるリストラの一環として、組織再編を目的として行われます。
整理解雇がなされる場合には、一般的な解雇権濫用法理とは異なる要件が必要とされ、次の4つの要件をいずれも満たすことが求められます。
①人員削減の必要性
②解雇回避の努力
③人員選定の合理性
④解雇手続きの妥当性
懲戒解雇
懲戒解雇とは、従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに行う解雇です。就業規則や労働契約書に、その解雇事由を具体的に明示しておくことが必要です。
労働者が懲戒解雇事由に該当したとしても、労働基準法に規定する解雇予告または解雇予告手当の支払いは必要です。
ただし、その懲戒解雇の事由が事業場内における盗取や横領、傷害等刑法犯に該当する行為など、労働者の故意や過失であった場合は、解雇予告または解雇予告手当の支払いは不要です。なお、この場合は、労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。
普通解雇を行うケース

普通解雇の主な理由としては、次のようなものが挙げられます。
仕事に必要な能力の欠如
本人の非行
頻繁な無断欠勤
職場規律の紊乱
休職期間の満了
協調性の欠如
普通解雇でも、就業規則等に「解雇事由」をあらかじめ明記しておく必要があります。
判断基準と妥当性
先述の例に挙げた「休職期間の満了」であれば、判断の基準は明確に判断できます。しかし、多くの普通解雇の場合、具体的な判断基準がなく、どこまでなら解雇しても良いのか判断が難しいものです。
また、過去の判例から判断基準を引き出すことも困難です。それは業種や職種の違いによって、合理的か否かの判断が分かれるからです。
たとえば、派手な色の染髪を就業規則で禁止している会社もあります。アパレルの店員であれば合理的ではないと判断されることでしょう。一方で、葬儀屋のスタッフであれば、派手な色の染髪を禁止し、この命令に従わない労働者に、なんらかの処分を課すことも合理的と考えられます。
このように、合理的な理由があると判断できるか否かは個別の事情により、最終的に裁判所の判断に委ねられます。
手順
労働者の言動が会社の定める解雇の事由に該当していたとしても、すぐに解雇できるわけではありません。会社側も相当の努力をすることが求められています。そして、会社側が手を尽くしたにもかかわらず状況改善の見込みがないときに、労働契約の継続が困難であると判断されます。
ここでは、頻繁な無断欠勤のような「問題行動」と「能力不足」に分けて、解雇に向けて会社が取るべき手順を解説します。
問題行動の場合
まずは、解雇を行う対象の労働者に対して何度か注意や指導を実施しましょう。このときに、本人の言い分や、本人が考える解決策などを聞いた上で、会社側の考えを伝えてください。
これでも改善が見られないようであれば、始末書を提出させます。書面など証拠が残る形での指導を何度か行うことで、会社側が複数回指導を行ったことが第三者からもわかるようにします。
それでも改善しない場合には、減給や出勤停止などの処分を行います。ただし、このような処分を行うには、就業規則に記載が必要であることには注意が必要です。
まだ状況が改善されなければ、解雇もあり得る旨を懲戒処分通知書に記載し、対象となる労働者に渡します。
能力不足の場合
能力不足が疑われるとしても、会社は対象の労働者に対して十分な教育を行う必要があります。労働者が仕事に必要な能力を獲得するためには、一定の期間が必要と考えられるため、教育訓練を実施するだけでなく、教育訓練を実施しながら様子を見ることになります。
この場合も証拠として残すため、対象の労働者に対して実施した教育訓練の内容を記録しておきます。
それでも改善が見られない場合は配置転換を行い、他の職種での就業の機会を与えましょう。特に、ある程度大きな企業であれば、複数の部署や職種に配置転換を行います。このような手順を経て、やっと解雇が可能になります。
解雇理由の規定例
解雇も含めた「退職に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項です。よって、解雇についても就業規則に記載する必要があります。
厚生労働省モデルの就業規則の解雇に該当する箇所は次のようになっています。
厚生労働省モデル就業規則
(解雇)
第○条 労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
1 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。
2 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さないとき。
3 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)。
4 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
5 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格
であると認められたとき。
6 懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
7 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業
の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。
8 その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。
整理解雇を行うケース

整理解雇は、会社の経営が悪化し、人員整理を行う必要性が生じたために行う解雇です。整理解雇は労働者側に落ち度があるわけではなく、企業側の事情による人員削減です。
必要な要件
整理解雇を行うには、その妥当性が問われます。過去の判例から、次の4つの要件をいずれも満たすことが必要です。
①人員削減の必要性
人員削減措置の実施が不況、経営不振などによる企業経営上の十分な必要性に基づいていることです。
人員削減の必要性が認められるためには、「売上の減少」や「大きな赤字」など客観的な根拠を用いて、余剰人員数を的確に算定します。また、人員削減と相反する「採用活動」や「賞与の増加」のような企業活動を実施していた場合、人員削減の必要性を疑問視されるため注意が必要です。
②解雇回避の努力
配置転換や希望退職者の募集など、他の手段によって解雇回避のために努力したことです。
整理解雇は、企業が生き残るための最終手段と考えられます。整理解雇を実施する前に、次のような解雇を回避するための経費削減の取り組みを行ったかどうかも判断基準となります。
残業規制
配置転換
出向
役員報酬の削減
一時帰休、自宅待機
希望退職者の募集
③人員選定の合理性
整理解雇の対象者を決める基準が客観的、合理的で、その運用も公正であることです。
整理解雇では、恣意的に解雇をする人員選定は認められません。あらかじめ解雇基準を明示し、その基準に照らして人員を選定します。たとえば、次のような項目などが基準となります。
能力
勤務態度
勤続年数
年齢
所属部署
④解雇手続きの妥当性
労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模・方法について納得を得るために説明を行うことです。
決算資料などを用いて経営状況を伝え、整理解雇に至る経緯について十分説明します。この説明は、複数回にわたって行うことが望ましいといえます。
手順
上記の4つの要件を踏まえ、次の手順で整理解雇を行いましょう。
①現状の把握
売上や利益、キャッシュフローの見通しなどを把握し、客観的な根拠を用いて余剰人員数を的確に算定します。
②解雇基準の設定
余剰人員を把握した後、配置転換やワークシェアリングなどを検討します。それでも解雇せざるを得ない場合には、解雇基準を設定し準備を進めます。
③解雇実施の発表
整理解雇を労働者へ通知します。労働者に対し、事業閉鎖の可能性や整理解雇の説明をし、早期退職希望者や異動希望者などを募ります。
④解雇者の人選
具体的な解雇対象者を選定します。そして、対象となった労働者本人への告知と誠実な説明を行い、労働組合とも協議を重ねます。
⑤解雇の予告
会社が労働者を解雇する場合には、解雇の予告が必要です。そのため、解雇予告通知書を作成し、対象となる労働者に交付します。
⑥解雇辞令の交付
解雇辞令を本人に発行し、予定していた退職金を支払います。
懲戒解雇を行うケース
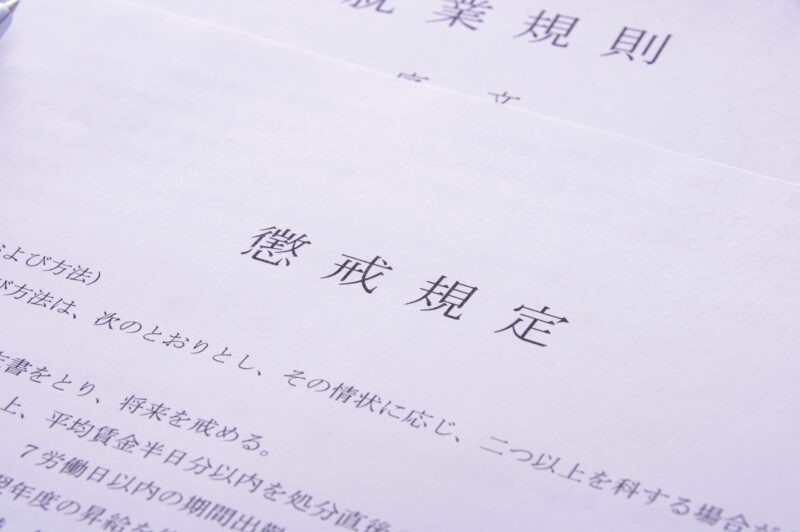
懲戒解雇は、従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに行う解雇です。
過去の判例によれば、使用者は規則や指示・命令に違反する労働者に対しては、「規則の定めるところ」により懲戒処分をなし得ると述べられています。したがって、 あらかじめ就業規則や労働契約書にその事由を具体的に明示しておくことが求められています。
条件
懲戒解雇を行う条件には、あらかじめその事由を明示しなければなりませんが、就業規則の「表彰及び制裁」に該当します。解雇は「退職に関する事項」ですので、就業規則にこの2つの項目を記載することとなります。
懲戒の事由の内容について、労働基準法上の制限はありません。しかし、懲戒事由に合理性がない場合、 当該事由に基づいた懲戒処分は懲戒権の濫用と判断される場合があります。
手順
労働者が懲戒解雇の事由に該当している言動を取った場合は、解雇しても問題ありません。
ただし、懲戒解雇の場合でも丁寧に事実確認を行い、証拠を用意しておかなければ、後々トラブルとなりかねません。
そのため、不正行為などが発覚したときは、まず関係者に事実を確認します。そして、不正行為を行った労働者に、不正行為に対する顛末書などトラブルの一部始終を報告する書類を提出してもらい、証拠とします。
次に、その行為が就業規則の懲戒事由に該当するのか、慎重に検討します。そして、不正行為を行った労働者に対して会社から説明を行うとともに、対象労働者に弁解の機会を与えましょう。そのうえで、懲戒解雇が適切な事象であれば、社内規定にしたがって処分を行うことになります。
解雇予告除外認定とは
解雇予告除外認定とは、労働基準監督署長の認定を受け、解雇予告を行うことなく労働者を即時解雇できる制度です。その懲戒解雇の事由が社内における盗取や横領、傷害等刑法犯に該当する行為など労働者の故意や過失であった場合は、解雇予告または解雇予告手当の支払いは不要です。
解雇予告除外認定基準は、企業の懲戒事由の内容とは別に法令等で定められています。そのため、会社の規則で定める懲戒解雇の事由に該当していれば、必ずしも解雇予告除外認定を受けられるわけではないことには注意が必要です。
解雇予告除外認定を受けるときには、懲戒解雇の前に除外認定書を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出を行います。
まとめ
正社員をなんらかの事情により解雇させるには、労働基準法などの法律を把握し、解雇の種類に応じた適切な手順を取らなければなりません。解雇を実施するには、会社側もかなりのコストと労力が求められる上、その対応が合理的と考えられるか専門家でないと判断が難しいといえます。
また、後々裁判となり「不当解雇」と判断されると、企業は高額な支払い命令を受けるリスクがあります。そのため、早めに弁護士などの専門家に相談を行いましょう。
本件を始めとした労務トラブルは、企業経営に大きく影響しかねない重要な問題です。もちろん裁判になってからの対応も可能ですが、当事務所としては裁判を起こさない「予防」が最重要だと考えております。
労務関連で少しでもトラブルがある企業様、不安のある企業様は、まずは当事務所までご相談下さい。訴訟対応はもちろん、訴訟前の対応や訴訟を起こさないための体制づくりのサポートをいたします。