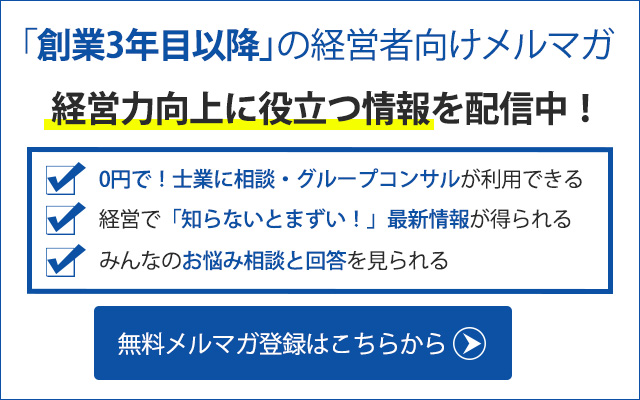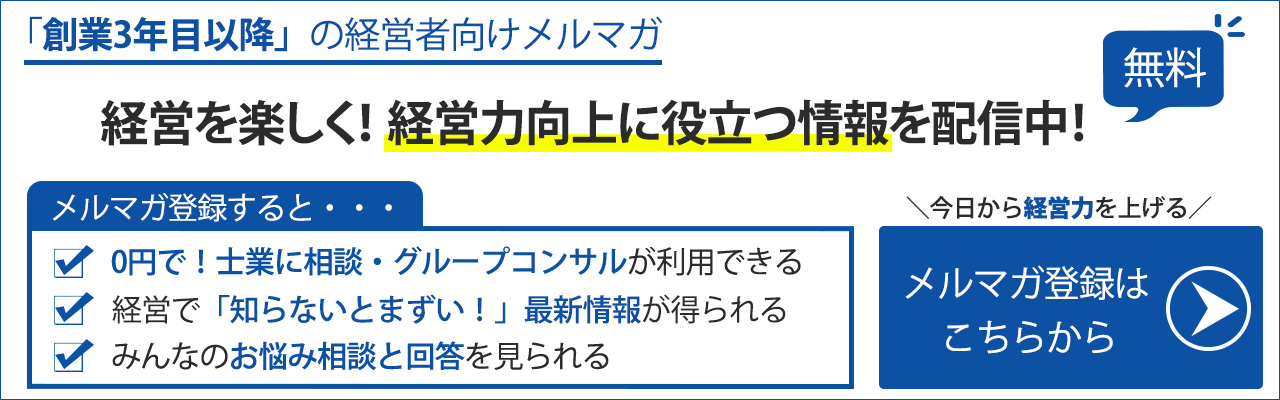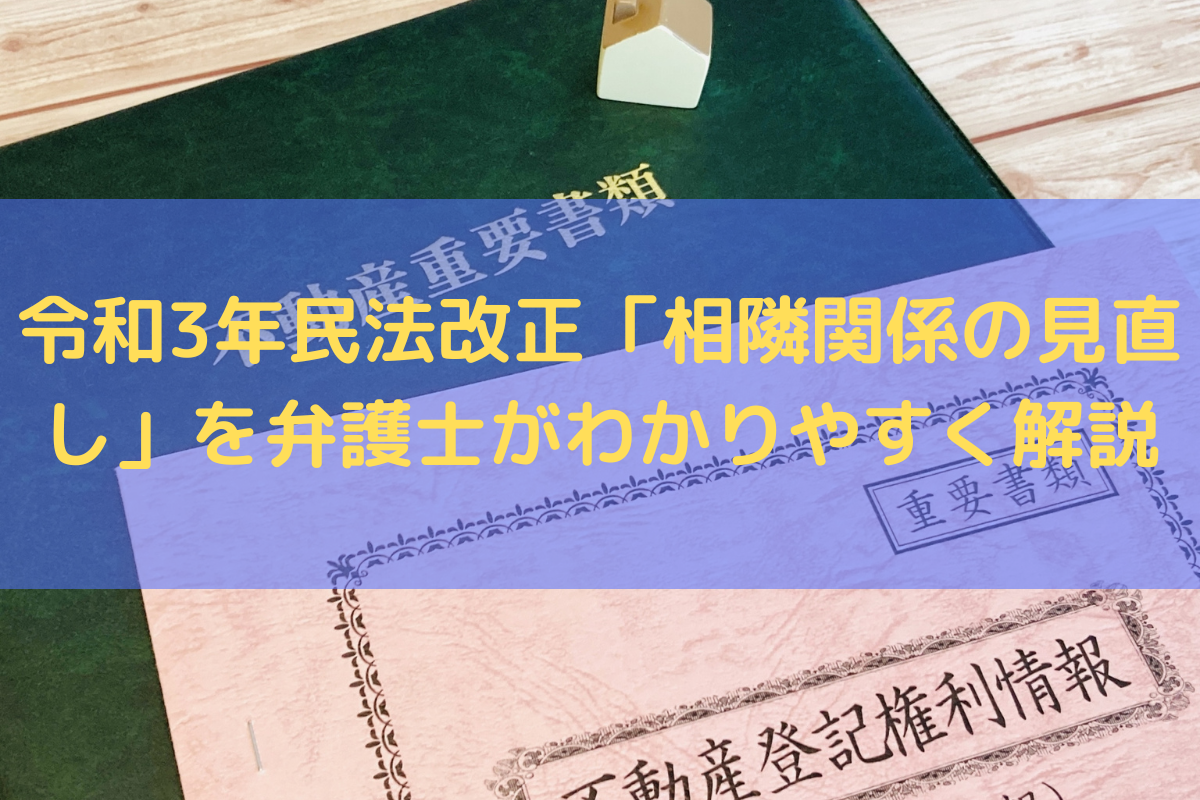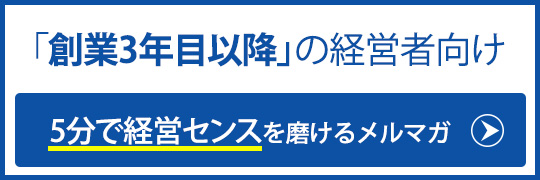【2023】担保責任(契約不適合責任)とは?期間や免責について弁護士がわかりやすく解説
不動産売買をするにあたっては、担保責任(契約不適合責任)についてよく理解しておかなければなりません。担保責任とは、売却した不動産が契約内容に合致していなかった場合に、買主から追及され得る責任のことです。
では、担保責任として、具体的にどのような請求がなされる可能性があるのでしょうか?また、買主から担保責任を追及されないためには、どのような対策をすれば良いのでしょうか?
今回は、不動産の担保責任について弁護士がくわしく解説します。
目次
担保責任(契約不適合責任)とは何か
はじめに、担保責任(契約不適合責任)の概要を確認しておきましょう。契約不適合責任とは、売買した不動産などが契約内容に合っていない場合に、追及され得る責任のことです。
従来は「瑕疵(かし)担保責任」と呼ばれていたものが、2020年4月施行の改正民法により、「契約不適合責任」へと改められました。これにより、内容も多少改められています。
代表的な変更点としては、従来の瑕疵担保責任では「隠れた瑕疵」の存在が要件とされていたところ、改正後の契約不適合責任では契約どおりであるかどうかが重要であり、瑕疵が隠れているかどうかは問題にならないという点です。
そのため、改正後に担保責任を追及されるリスクを減らすためには、売却する不動産の現況をよく確認したうえで、契約書をよく作り込むことがより重要となります。
契約不適合があった場合に追及される担保責任の内容
契約不適合があった場合に追及される担保責任の内容には、どのようなものがあるのでしょうか?契約不適合に対してなされる可能性のある請求は、次のとおりです。
追完請求
引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、追完請求がなされる可能性があります。追完請求とは、売主に対して次の対応を請求することです。
目的物の修補
代替物の引渡し
不足分の引渡し
これらのうち、いずれの対応を請求するのかは、原則として買主側が選択します。ただし、買主側に不相当な負担を課するものでないときは、請求された内容とは異なる対応をすることが可能です。
そのため、不動産について追完請求がされた場合には、原則としてこのうち「目的物の補修」で対応することとなるでしょう。なぜなら、引き渡した土地や建物に契約不適合があったからといって、代わりの土地や建物を用意することは困難であり、「代替物の引渡し」は現実的ではないためです。
また、仮に面積が不足していたからといって足りない面積を追加して引き渡すケースも想定しづらく、「不足分の引渡し」も現実的ではありません。なお、契約不適合が生じた理由が買主側の責任によるものであるときは、履行の追完を請求することはできません。
代金減額請求
引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものである場合において、履行の追完を請求しても期間内に履行の追完がされない場合には、代金減額請求が可能となります。
代金減額請求とは、その不適合の程度に応じて、代金の減額を請求することです。たとえば、200平方メートルとの前提で売買契約を締結した土地について、購入後に実測したところ199平方メートルしかなかった場合において、元々2,000万円であった購入対価を10万円(=2,000万円×不足分の1平方メートル/200平方メートル)減額するよう請求することなどがこれに該当します。
ただし、次の場合には履行の追完の請求を経ることなく、はじめから代金減額請求をすることが可能です。
履行の追完が不能であるとき
売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時や一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき
催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
たとえば、上で挙げたように土地の面積が不足していた場合には、履行の追完は不能であるケースが多いでしょう。隣地が他者の所有である場合、この土地を1平方メートルだけ分けてもらって追完を受けるようなことは、考えにくいためです。
このような場合には、履行の追完を請求せず、代金減額請求をすることができます。なお、契約不適合が生じた理由が買主側の責任によるものであるときは、代金減額請求をすることはできません。
損害賠償請求
債務者である売主がその債務の本旨に従った履行をしないときや、債務の履行が不能であるときは、損害賠償請求をすることができます。
担保責任の追及としての損害賠償請求とは、売主が約束(契約)どおりの履行をしなかったことによって買主が損害を受けた場合において、その損害の賠償を金銭で請求することです。
ただし、債務の不履行が売主の責任であるとはいえない事情によるものであるときは、損害賠償請求をすることができません。
契約解除
売主が債務を履行しない場合において、相当の期間を定めて催告をしてもその期間内に履行がないときは、契約の解除をすることができます。たとえば、契約上の引渡し日において売主が不動産を引き渡さず、催告をしても引き渡さない場合などがこれに該当します。
また、債務の履行が不能であるときや売主が履行を拒絶する意思を明確に示した場合などには、催告をすることなく契約を解除することが可能です。ただし、不履行の程度が契約や社会通念に照らして軽微である場合には、解除までは認められません。
担保責任(契約不適合責任)はいつまで追及される?
契約不適合責任への改正後、不動産の担保責任はいつまで追及される可能性があるのでしょうか?
まず、民法566条では、種類や品質の不備に対して担保責任を追及するためには、「買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知」しなければならないとされています。
仮にこの規定をそのまま適用した場合には、売買契約からかなりの時間が経過してから担保責任を追及される可能性があるでしょう。なぜなら、この規定では契約不適合を知る時期に関しては制限がなく、たとえば売買から5年もの期間が経ってから買主が契約不適合に気付いた場合、そこから1年間は担保責任の追及ができてしまうためです。
そのため、通常は売買契約において、担保責任を追及することができる期間に一定の制限を設けることが多いでしょう。
ただし、宅建業法40条では宅建業者が売主となり契約での担保責任の追及期間について、「その目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない」と規定しています。そのため、宅建業者が売主となる場合には、契約において、担保責任の追及期間を「引き渡し後2年」などと定めていることが多いでしょう。
このように、担保責任の追及期間は契約書での定めが非常に重要となります。そのため、弁護士などの専門家へ相談のうえ、契約書をしっかりと作り込むことが重要です。
なお、仮に契約書で期間の制限を設けても、契約不適合について売主が知りながら告げなかった場合や知らないことに重過失があった場合には、期間の経過後も担保責任を追及される可能性があります。
買主から担保責任(契約不適合責任)を追及されたら
不動産の売買をする場合、買主から担保責任(契約不適合責任)を追及されたら、どのように対応すれば良いのでしょうか?基本の対応方法は、次のとおりです。
事実関係をよく確認する
不動産の買主から担保責任を追及する旨の連絡があったら、まずは事実関係を確認しましょう。どのような点について契約不適合となっているのか、確認しないことには対応のしようがないためです。また、契約不適合が、買主側の勘違いである可能性もゼロではありません。
事実関係の確認方法としては、たとえば現地や自社にある資料を確認したり、実際に売買を担当した従業員から経緯を聞いたりすることなどが考えられます。いずれにしても、確認をする前に対応方法などを買主側に即答するようなことは避けた方が良いでしょう。
弁護士へ相談する
事実関係の確認と併せて、不動産法務にくわしい弁護士へ相談すると良いでしょう。弁護士へ相談することで、買主側による契約不適合に関する指摘や買主側がしている請求が正当なものであるかどうかなどを、確認することが可能となります。
また、請求に対する対応方法についてもアドバイスを受けることができるほか、対応方法について相手方との交渉がまとまらない場合には、弁護士に代わりに交渉してもらうことも可能です。
また、仮に裁判へともつれ込んだ場合であっても、弁護士に依頼をしていれば、落ち着いて対応することができるでしょう。
買主から担保責任(契約不適合責任)を追及されないために
売買契約後に買主から担保責任を追及されないため、売主側はどのような対策をすれば良いのでしょうか?主に講じるべき対策は、次のとおりです。
現地をよく確認する
契約後に担保責任を追及されるリスクを減らすためには、売却前に現地をよく確認することが重要です。
現地をよく確認したうえで少しでも気になる点があれば、その旨を買主にあらかじめ説明するとともに、契約書面に明記しておきましょう。
契約書を作り込む
不動産の担保責任が瑕疵担保責任から契約不適合責任へと改正されたことで、契約書がより重要となりました。なぜなら、契約内容に適合していない場合にのみ担保責任を追及されることとなったため、契約内容としていた事実については、仮に一般的には問題とされるような状態であったとしても、免責されるためです。
たとえば、雨漏りする建物をそのことを隠して売却したら、購入後に雨漏りに気づいた買主から担保責任を追及されて、問題となる可能性が高いでしょう。一方、買主もはじめからその建物が雨漏りすることを知っており、契約書にもそのことが明記されていたのであれば、これに対しては担保責任が追及されないということです。
また、上の「担保責任(契約不適合責任)はいつまで追及される?」でも解説したように、担保責任の追及期間についても一定の制限を設けておくべきでしょう。このように、担保責任を追及されるリスクを低減するためには、契約書の規定が非常に重要となります。
買主に事前にしっかりと説明する
担保責任を追及されるリスクを減らすためには、売却する不動産の状態を、買主にしっかりと説明することです。契約書に記載すべきであることはもちろん、特に問題のある部分についてはしっかりと説明をして、買主の理解を得ておくようにしましょう。
相談先の弁護士を確保しておく
買主から思いがけず担保責任を追及されるような事態を避けるために、相談先の弁護士を確保しておくと良いでしょう。そのうえで、少しでも心配な部分がある不動産を売却するにあたっては、あらかじめ弁護士に契約書面の確認をしてもらうことをおすすめします。
また、万が一買主から担保責任の追及がされた場合にもすぐに顧問弁護士へ相談することで、すみやかに適切な対応を取ることが可能となります。
まとめ
不動産の担保責任とは、引き渡した不動産が契約内容に合致しない場合に追及される責任のことです。具体的には、契約解除のほか、損害賠償請求や代金減額請求などがなされる可能性があります。
不動産の売却後に担保責任を追及されるリスクを減らすためには、不動産の状況に合わせて契約書を作り込み、買主によく理解を得て契約を締結する必要があるでしょう。
担保責任が従来の瑕疵担保責任から契約不適合責任となったことで、契約書の内容がこれまで以上に重視されることとなりました。そのため、不動産売買の契約書は契約締結の前に、弁護士の確認を受けることをおすすめします。
たきざわ法律事務所には不動産法務にくわしい弁護士が在籍しており、不動産にまつわるトラブル解決やトラブル予防に力を入れております。担保責任を追及されてお困りの際や、担保責任を追及されるリスクを減らしたいとお考えの際には、ぜひたきざわ法律事務所までご相談ください。